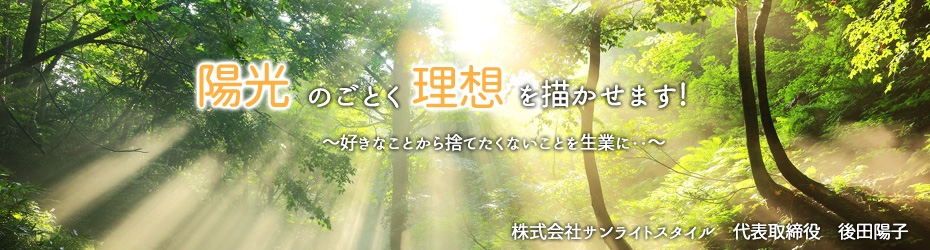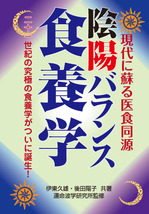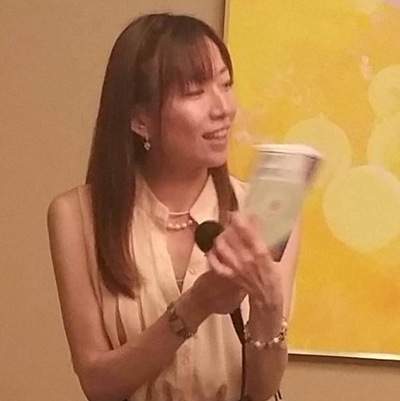地方拠点への出張の際、地元の猟友会の方からいただいたシカ肉(約5kg)のジビエを新年会で美味しく堪能させていただきました!

細かい筋膜や筋などが張りめぐされているため、代表が丁寧に処理してくださいました。
スルスル剥がすことはできないため、本当に労力のかかる作業で数時間立ちっぱなしでした!
筋膜や筋などがあるとゴリゴリとして噛み切れず食感も味も落ちるのですが、あまりにもたいへんな作業のため通常取り除くことはしないそうです、ちなみに猟師さんたちにどのようにして食べるのか伺ったところそのままぶつ切りにしてお鍋などで食べるとおっしゃっていました!
 ものすごくきれいなお肉です。
ものすごくきれいなお肉です。
くさみがまったくなく、この状態でお肉のにおいを確かめると、馬刺しのような?マトンのような?香りがします!
 ↓ちなみに取り除いた組織のほんの一部。
↓ちなみに取り除いた組織のほんの一部。
台所のディスペンサーに入れてもまったく細かくなりませんでした。
食べても問題ないものですが、やはりこれだけ噛み切れない組織が入っているのといないのとでは味に大きな違いがでそうです!

こちらはニンニク、ショウガ、黒コショウ、だしで煮込んだものです!
猟師さんから伺っていたとおり、シカ肉はまったくくさみがなく、これまで食べたことのあるお肉(牛、豚、鶏、馬、羊)のなかで一番美味しかったです!!
しっかりと筋膜などの組織を取り除いていただいたので、とても柔らかくしっとりふっくらしていました。

↓こちらは薬膳鍋!
スライスしたショウガとニンニク、塩、香りづけの醤油を入れ煮込みます。
中国では有名なスパイスの五香粉(八角、クローブ、シナモン、コリアンダー、山椒)も加えています。
このときに、一緒に茹で卵を入れると、美味しい煮卵もできます。
ダイコンもとろとろになって美味しいのでおすすめです。
肉が柔らかくなるまで煮込んだら火を止め冷まします。
この冷ます過程で味がこなれて美味しくなります!
他のお肉ですと、冷めると表面に白い油が固まったりしますが、シカ肉はまったくそれがなくびっくりしました!
 新年会の翌日以降も、何日もお鍋を楽しむことができました。
新年会の翌日以降も、何日もお鍋を楽しむことができました。
猟師さんに狩っていただいた、しかもはじめての鹿肉をいただけるという貴重な経験ができ、本当にありがたく素敵な一年のスタートとなりました!

*********
先日、茨城県のレンコン農家さんから収穫直後の新鮮なレンコンをプレゼントにとたくさんいただきました!
昨年もいただき、毎年のように冬は楽しみが増えました!
このような連なったままの姿のビッグサイズのレンコンはなかなかお目にかかれません。
一つだけでもスーパーに売られているレンコンとまるで別物、一塊でもトレイに入らない規格外サイズです。

レンコンは、食物繊維とビタミンCやポリフェノールなど豊富な栄養が含まれ、そのシャキシャキやホクホクの食感も楽しめることから皆さんから親しまれた食材です。
食品の渋みやえぐみとなるレンコンのアクにはこちらのポリフェノール類が含まれていて、空気に触れることで、このように色が茶色くなります。

「アク抜きをすると栄養成分が流れ出る」と言われるようになり、アク抜きをするのが良いとか悪いとか最近ではさまざま言われます。
色や食感や味にこだわるならアク抜きをして、栄養が優先であればアク抜きをしないといった形で、過度に神経質になりすぎずに柔軟にその都度調理に合わせて楽しみたいものです。
ちなみに、収穫の時期にもよりますが新鮮レンコンにはアクは少ないのでそんなに気にしなくて良いと思います。
事実、生産農家さんでもアク抜きしないそうです!
また、アクが多いのは皮の部分。
アクが多いということは栄養(ポリフェノール)も含まれていることになりますが、
こちらもまた皮は栄養があるから剥かない方が良いとか悪いとかさまざま言われるポイントではありますが、
同様に気にし過ぎずに、見た目など気になる方や、調理に合わせて薄くレンコンの皮をむくことをおススメします。
さて、レンコンの皮は薄いのでどうしても厚くむいてしまいますが、薄く皮を処理するためにはちょっとコツがあります。
プロの方はどうしているのか教えていただきました。
最初にピーラーでさっと剥きます。
すると、このような状態になります。

このあとに、細かいところを包丁でこするように剥きます。
ちょっと手間がかかりますが、こうすることで大切な栄養素の多いところが得られるのです。
レンコンは場所によっても食感がかなり違います。
冒頭の写真、左の方が一番ホクホク、右にいくにつれシャキシャキのレンコンになります。
これは、左の方からでんぷんが多く、先の方に行くにつれ少なくなるためです。
料理によって食感を使い分け美味しくいただきたいですね。
***
冬野菜は栄養満点!
寒くなってから収穫される野菜は苦みや辛みが強い野菜が多いですが、これは薬効成分が豊富な証拠でもあります。
クセのある葉野菜は、加熱すると苦みなどが抜けて甘くなります。
更に強い陰が陽の要素を得て、陰陽バランスが向上します!
そこで各種の秋から冬にかけて採れる葉野菜を「湯びき」にして美味しく味比べしてみました!
この日は、
ルッコラ、ターサイ。

この日は野沢菜もいただきました。

また、別の日には、ターサイの若芽の部分と、食用タンポポ。

さらに別の日は、大きな野沢菜と高菜。

辛いワサビ菜。

これだけたくさんの冬野菜の湯びきをいただきまして、不思議なことに気が付きました。
生では苦辛いルッコラ、野沢菜、ワサビ菜などはさっと湯通しするだけでものすごく甘くなります。
でも、食用タンポポだけは・・、
煮ても炒めても、何をしてもほろ苦さが残っているのです!
食用タンポポの薬効成分、おそるべし!!
薬効成分の違いが舌でも確認できました!
***
「腐乳(フールー)」をご存知でしょうか?
豆腐を麹につけ、塩水のなかで発酵させた中国の食品で、別名は豆腐乳(ドウフールー)です。
半年ほど発酵させ、コクのある深い独特の味わいが生まれます。
豆腐を麹につけ、塩水のなかで発酵・・・
考えただけですごそうです(笑)
しかしなぜかやみつきになる「腐乳」は「東洋のチーズ」と呼ばれるほど濃厚で深い味わい、ねっとりとした食感が特徴的です。
たんぱく質が多く健康食品としても親しまれ、お酒との相性も抜群で知る人ぞ知る夜の人気のおつまみです!
自家製でも作れますが、購入してきたものをさらに冷蔵庫で賞味期限を気にせず発酵させるのが簡単で良いと思います。
こちらは中国で購入してきたものをさらに10年ほど冷蔵庫で寝かせたもの。
正直、物凄い香りが漂います!
しかし、これがブルーチーズのようですごく美味しいのです!

この「腐乳」が明から伝わり、現在沖縄のソウルフードとなっているのが「豆腐よう」です。
「腐乳」にはお酒が使われていないのに対し、沖縄の「豆腐よう」には沖縄特産のお酒である泡盛や紅麹などに漬け長時間発酵させます。
漬け汁によって色も味も変化し独特の味わいが発生します!
さらにこちらは「糟方腐乳」というもので、醤油で漬けこんでいます。
同じく、中国で購入してきたものを冷蔵庫で5年以上寝かせたものです。
上の「腐乳」よりも、強烈なクセが口に広がります。
(本場中国人でも苦手な人も多いほどだとか!)
たしかに、甘いような、すっぱいような、辛いような・・
なんとも表現しがたい味わいです!

発酵食品ならではのクセがありかなり濃厚なので、つまようじでチビチビとほんの少しの量を舌の上にのせて口の中でゆっくりと味わうのがおいしく食べるコツです。
野菜スティックや肉料理など、ほんの少しつけて食べるのも美味しいです。
こちらは唐辛子の入ったピリ辛バージョンで、生野菜との相性が抜群です!

わたしはよく鶏ハムや野菜につけて食べています!
やみつきになる「腐乳」は、お酒好きな方にもゆっくりとお酒を飲みながらつまむにはもってこいです!
*********
話題の、和製オリーブ作り。
日本のあちこちでオリーブを育て、日本産オーガニックオリーブを広げようという運動が盛んになりました。
今回は、宮崎県で行われているオーガニックオリーブ作りのプロジェクトの初収穫した塩漬けの限定サンプルを送ってもらいました。
収穫量が少ないので今年は関係者だけにサンプルで配っただけで発売には至っていません。
発売開始が楽しみです。
一山ほどの作付け面積で20年も丹精に育てて、やっと市場に出せるほどの収穫になる・・
自身は代は努力だけで利益は次の世代に残すプロジェクト、
こういうのが男のロマンなのでしょうか?
そして、種類の異なるオリーブを同じ場所で育てないと実が付かないのだと言います。
オリーブの生態は現在研究段階にあります。
気の遠くなるようなプロジェクト、成功してほしいと思います。
初収穫なので粒の大きさはバラバラですが、新鮮なオリーブを堪能できました。
酸化防止で薄い塩の液体に漬けてあるだけなので、塩抜きせずにそのまま食べられます。
ワインにとても合うおつまみだと感じました。
ワインバーやイタリアンレストランでメニューに加えられるといいな・・

そしてオリーブは、
オレガノやタイムなどのスパイスとの相性がとても良いです。
塩漬けにオリーブオイル、
香りスパイスを少し振りかけるだけで最高のおつまみに!

***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店でお買い求めいただけます。
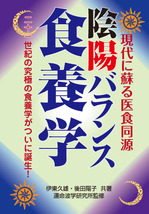
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/


 ものすごくきれいなお肉です。
ものすごくきれいなお肉です。 ↓ちなみに取り除いた組織のほんの一部。
↓ちなみに取り除いた組織のほんの一部。

 新年会の翌日以降も、何日もお鍋を楽しむことができました。
新年会の翌日以降も、何日もお鍋を楽しむことができました。