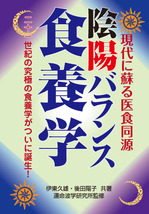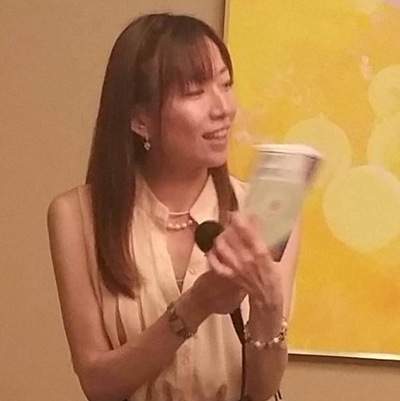植物の生命力と古人の知恵をいただきながら
心(陰)と体(陽)の陰陽バランスを整えるお酒を楽しんでいます。
先日、まだ試飲していなかった薬酒をみんなで少しずついただきました!
こちらは35年以上漬けたビンテージ物の薬酒です。
上にあるのが料理などの食用に栽培された高麗人参、
下にしずんでいるのが超高級漢方薬の冬虫夏草。
他にもナツメ・陳皮(柑橘類の皮を乾燥させたもの)なども混ぜています!

じつはこの薬酒、なぜ飲めていなかったかというと、冬虫夏草だったからです。
冬虫夏草はきのこですけど、虫でもあったわけだし・・?
というか虫という名前がついている時点でもう無理だし・・笑
といった具合で虫嫌いのわたしにはちょっとハードルが高く飲めていませんでした。
今回、勇気を出して試飲です。
そのお味は・・
え・・?!ビックリ!!
その見た目と裏腹に、ほんのり甘くて美味しい!!
薬酒は熟成すればするほど甘くなっていきます。
やはり35年以上という年月がこの風味を作っているのだと思います!!
こちらは普段少しずついただいている5年物のタンポポの根酒です。

はい、安定の苦さ!笑
タンポポ根酒を飲むことができれば、他のどの苦いと言われる薬酒も甘く飲めるように思います。
これまでさまざまな薬酒を飲んできましたが、タンポポ根酒が圧倒的に苦くて刺激的です!!
何年漬けても苦いままなのはタンポポだけ(笑
それほどタンポポの根にも薬効成分が豊富に含まれている、ということなのですね!!
この日は一日身体がポカポカになりました!
***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店及びAmazon・楽天等の通販書店でお買い求めいただけます。
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/

植物の生命力と古人の知恵をいただきながら
心(陰)と体(陽)の陰陽バランスを整えるお酒を楽しんでいます。
ちょうど1年前に頂いたオーガニックオレンジとゆず。
無農薬ということで、その皮を乾燥させて薬膳酒を作りました。

1年後!

柑橘類の皮を乾燥させたものは陳皮(ちんぴ)という漢方薬です。
咳止めやアレルギーなどの緩和に処方されるそうです。
夏はミネラルや炭酸で割って爽やかなクールドリンク。

冬は、皮ごと入れてホットで飲むと身体が暖かくなります。
ホットで飲む時はハチミツを入れるとさらに美味しいです!
 フレンチやイタリアン料理の香り付けにも!
フレンチやイタリアン料理の香り付けにも!
少し加えるだけで爽やかな香りがして最高です。
ドリンクや料理にも多用できます。
***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店及びAmazon・楽天等の通販書店でお買い求めいただけます。
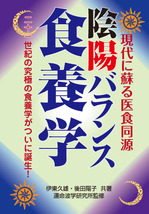
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/

定番のネギ味噌から、ちょっと変わった鶏味噌、タンポポ味噌などなど、おつまみにもご飯のお供にもなるいろいろな味噌を常備しています。
ご飯が好きな方にも、お酒が好き方にも、そして便利調味料としても大活躍のお味噌です。
写真左はサバ味噌。
右が胡麻クルミ味噌です。
サバ味噌というと、サバを味噌で煮込んだ煮込み料理を思い浮かべかちですが、本来の「サバ味噌」とはこの常備味噌が由来とされています。

熟成させればさせるほど美味しくなっていきます。
写真ではわかりづらいのですが、どんどん色が濃く変化していき、また具材も細かく柔らかになり食感が変化していきます。
作りたてももちろん美味しいですが、まだ具材とお味噌の味が分離して味が尖っています。
熟成していくとどんどんこなれて一体化しまろやかになります!

先日新米(玄米)をいただいたので、さっそくこれらのお味噌といただくことにしました。



お味噌は自家製味噌を使うのがポイント。
熟成してどんどん味が進化していく過程を楽しめます。
熟成味噌と具材から生まれる旨味の組み合わせが絶品!ごはんのお代わり必至です。
これらのお味噌は後日「陰陽バランス食養学」ブログ等でご紹介していければと思います。
***
サンライトスタイル公式ブログ
https://function5.biz/blog/sun/

植物の生命力と古人の知恵をいただきながら
心(陰)と体(陽)の陰陽バランスを整えるお酒を楽しんでいます。
いろいろなフルーツや薬草を、大好きなお酒にしては試飲しています。
最近ではスパイスのお酒も。
こちらは桂皮(シナモン)酒。

わずか数日でこのような綺麗なブラウン色に

シナモンは、中国南部からベトナムに自生するクスノキの一種の樹木の皮です。
漢方薬では桂皮として広く知られています。
市販されているシナモンスティックは正確にはシナモンの樹皮ではなく、
他の木を薄くスライスして成形しシナモンの香りだけをつけたものもあります。
どうりで形が揃っていますね。
本物の桂皮は、まさに樹の皮そのものでこんなにゴッツイです。


ここで注意です。
シナモンのスパイシーな香りの、香り成分であるクマリンを過剰摂取することで、
肝機能に影響を与える可能性がありますので、
シナモンはしっかり適量を守って摂取しましょう。
クマリンとは、ファイトケミカルの一種「ポリフェノール」に分類される香り成分。
毛細血管の保護と修復、殺菌・解熱作用、血流の改善、血糖値・コレステロール値の抑制、抑うつ、更年期障害の改善など、
メリットがたくさんあるクマリンですが、
過剰摂取は逆に身体に負担をかけてしまいます。
シナモンの一日の摂取量は、
小さじ1杯(3g)を目安にして、
1日に10g以上を長期に渡って摂取しないようにしましょう。
事務仕事中はホットでひと休み。
身体が温まります。

夏は、ジンと炭酸水と割ってアイスでも、甘くて美味しいです。

就寝中の成長ホルモンにより、
シナモンによる修復やアンチエイジング効果が増幅されることが期待できるとされていますので、
飲む時間帯は、特に就寝前に適量を摂ることがおすすめだと言われています。
***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店及びAmazon・楽天等の通販書店でお買い求めいただけます。
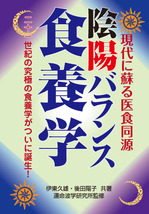
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/

陰陽バランス食養学の研究を日々楽しんでいます。
毎週、大量にオーガニック栽培のビーツを入手しては、
各種のアレンジレシピにチャレンジしています。
今回は、生のコリコリした食感をいつでも味わえるように、
ピクルスを作ってみました。
皮を剥いて適当な大きさにカット、
ビンに詰めて、沸騰させたピクルス液を注ぐだけ!

ピクルス液は、
酢に砂糖、塩を好みで適量入れて、
酢と同量の水を加えて出来あがり。
とても簡単です!

1週間もすれば、美味しく食べられます。
冷蔵庫で保管すれば、
何年でも生のような食感が楽しめます。
また、これを使った料理にもチャレンジします!
***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店及びAmazon・楽天等の通販書店でお買い求めいただけます。
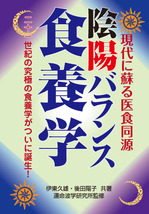
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/



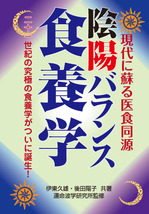

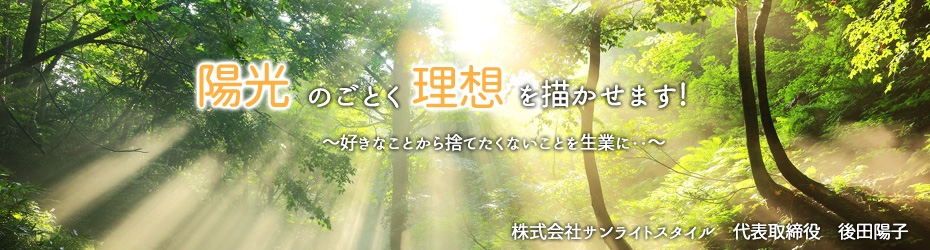



 フレンチやイタリアン料理の香り付けにも!
フレンチやイタリアン料理の香り付けにも!