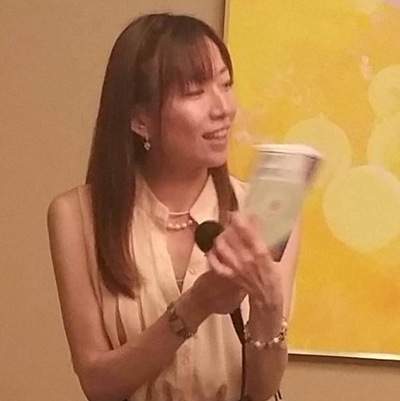今年はまだ種のできていない若い青梅や、小梅を塩に漬け、シンプルな塩梅をたくさん作りました。
↓大きい方は若い青梅の塩梅。このまま食べたり糠漬けにしたりしています。
小さい小梅の塩梅はカリカリ梅として食べています。

この塩梅を、6月に収穫した完熟梅でも同じ作り方で作ってみることにしました。

塩で漬けて冷蔵庫で保存します。
どんな味になるでしょうか。

一週間ほどで完成しました!
梅なのですが、ほのかに杏子と桃の良い香りが口に広がり、これまで食べたことのない美味しい梅になりました!!
杏子や桃といった、フルーツの味もプラスされた爽やかな風味なのに、やはり梅だけあってご飯にもよく合います!
 青梅は塩で漬けるとシャリシャリした食感になりますが、完熟梅は柔らかくなり、まさに見た目は梅干しのよう!
青梅は塩で漬けるとシャリシャリした食感になりますが、完熟梅は柔らかくなり、まさに見た目は梅干しのよう!
色は黄色く鮮やかでとてもキレイな塩梅になりました!!
******
本丸の庭に群生している赤ジソを使って、とても美味しい自家製練り梅を作りました。

作り置きしているこちらの梅ペーストに、赤ジソと出汁と甘みを加えるだけ、とても簡単です!

青梅ペーストと、完熟梅ペーストの双方で作ってみました。
完熟梅ペーストは桃や杏子の風味もあるので、練り梅もまたひと味違った美味しさです。
時々表面に白いものが出ることがありますが、産膜酵母という無害な酵母菌ですので気にせず食べても大丈夫なものです。
これは梅だけではなくすべてのフルーツで作ったジャムなどにも出るもので、フルーツに入っている糖を餌にする酵母が自然発生するもので極自然の摂理です。
酵母による発酵が進むとアルコールに変化していきます、時々動物が食べて酔っぱらうのだそうです。
ただ過度に発生すると味が落ちるので、その場合は加熱すると酵母が死んでおさまります。
しかしこれは保存料も何も入れていない証拠。安心して美味しく食べることができます!

そのままでも美味しいこの練り梅、何につけてもよく合います!
キュウリにつけると止まらないです・・

クエン酸は胃酸の働きを助け、消化酵素の活動を促すことでタンパク質の消化を助けてくれるので、お肉のソースにも持ってこいです!

梅の豊富なビタミンEやクエン酸、そして梅のクエン酸によって赤シソから抽出されるアントシアニンや鉄などは身体や精神を整えるポリフェノールやミネラルです!
美味しすぎてついつい食べ過ぎてしまいそうになるのですが・・毎日少しずつを心がけています。
赤ジソが手に入らなくても市販の「ゆかり」ふりかけを使っても作ることができるようなので、ぜひ美味しい自家製練梅を食べてみてほしいと思います!
******
6月、7月に収穫した完熟梅でも梅ペーストを作ってみました!

完熟梅は黄色くなり、ほんのり赤く色づいてとてもかわいいです。

こちらも水を少し加え焦げないようにかき混ぜながら加熱するだけで完成です!
大量でしたので、いつも通りこれでもかと梅を投入、大きなお鍋を3つ駆使して2日半くらいかかりました・・!
業務用の冷蔵庫はありませんので、家庭用の冷蔵庫では収まりきらず、ラボの一部屋を24時間エアコンでキンキンに冷やし、部屋を丸ごと冷蔵庫代わりにしてしまうという荒業を使いながらなんとか終えることができました!笑
ジプロックに入れて冷凍することにしたのですが、数えていないのですが数十袋くらいになりました!

↓写真左が今回の完熟梅ペースト。右が青梅ペースです。
色がだいぶ違います!
完熟梅ペーストは甘いのかな?と思っていたのですが、とんでもありませんでした!
青梅より多少酸味は少ない気がしますが、それでもやっぱりすごく酸っぱいです!
でも味はやはり違います!青梅ペーストと比べて、完熟梅ペーストは桃のような杏子のような味がします!
どちらも本当に美味しくて大好きです!

自宅の冷凍庫、ラボの冷凍庫、会社の冷凍庫、すべてが埋まり、皆さんにも配って・・・
それでも収まりきらないものも悪くならないうちにいただきました!
来年まで食べきれるか分からないほどまだまだあります!
でも味わって大事に食べていきたいと思います!
 このように袋で冷凍すると、食べる分だけパキッと折って食べることができるので、とても便利です!
このように袋で冷凍すると、食べる分だけパキッと折って食べることができるので、とても便利です!
*******
こちらは5月収穫時の青梅。

梅酒を作るだったのですがあまりに収穫した梅の量が多かったため、瓶にこれでもかと詰めたら、結果的に梅酒と言うより梅の焼酎漬けになってしまいました!笑
後ろにある瓶は前回作った梅酒ですが、梅の量が違います!

こちらは6月収穫時の完熟梅。

こちらも同じように梅酒のつもりが焼酎漬けになりました!

これらの瓶(4リットル&5リットル)があっという間に数十個くらいになり、東京のラボは埋め尽くされてしまいました。
最初はこんなに消費しきれるのか心配だったのですが、代表がいろいろな人にこの瓶ごと分けてあげていました、するとあっという間になくなってしまいそうです!
喜んでもらえたようで、よかったです!!
******



 青梅は塩で漬けるとシャリシャリした食感になりますが、完熟梅は柔らかくなり、まさに見た目は梅干しのよう!
青梅は塩で漬けるとシャリシャリした食感になりますが、完熟梅は柔らかくなり、まさに見た目は梅干しのよう!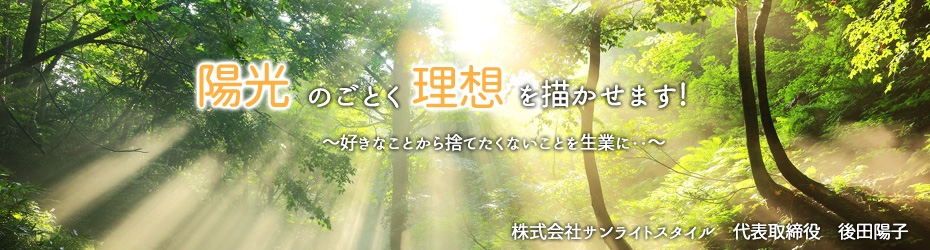









 このように袋で冷凍すると、食べる分だけパキッと折って食べることができるので、とても便利です!
このように袋で冷凍すると、食べる分だけパキッと折って食べることができるので、とても便利です!
 加熱するとあっという間に柔らかくなり色が変わってきます。
加熱するとあっという間に柔らかくなり色が変わってきます。 本当に良い香りです!
本当に良い香りです! すぐにトロトロになります!
すぐにトロトロになります! 種の周りの実をこそぎ落しながら、種を取り除いて完成です!
種の周りの実をこそぎ落しながら、種を取り除いて完成です!