2025年10月 3日 11:00
簡単で栄養抜群で美味しいピクルスをいろいろな食材で作っています。
今回は本丸で収穫した姫カボチャを追熟し、ピクルスにしてみました。

 水に黒砂糖とリンゴ酢と塩を適量入れて沸騰したら
水に黒砂糖とリンゴ酢と塩を適量入れて沸騰したら
素材を入れた容器に注ぐだけ。

1週間もすれば、美味しく食べられます。
冷蔵庫で保管すれば何年でも生のような食感が楽しめます!
***
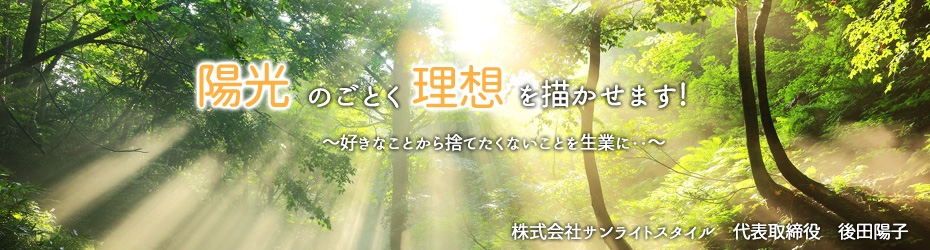
2025年10月 3日 11:00
簡単で栄養抜群で美味しいピクルスをいろいろな食材で作っています。
今回は本丸で収穫した姫カボチャを追熟し、ピクルスにしてみました。

 水に黒砂糖とリンゴ酢と塩を適量入れて沸騰したら
水に黒砂糖とリンゴ酢と塩を適量入れて沸騰したら
素材を入れた容器に注ぐだけ。

1週間もすれば、美味しく食べられます。
冷蔵庫で保管すれば何年でも生のような食感が楽しめます!
***
2025年10月 1日 11:00
先日収穫したカボチャの新芽は、花が咲いていました。
茎も美味しいですが、この花も美味しく食べることができます!
↓雌花には、蕾のうちから花の根本に丸い子房がついています。この子房がミツバチなどの受粉によってカボチャの実になります!
とくにこの雌の子房が、信じられないほど美味しいんです!!
しかしながら、この雌の子房はのちに実になってくれるのであまり摘心できない貴重な部分。
そして雌花より雄花のほうが数がありすべての雄花が受粉に使われるわけではないで、雄花の方が間引きされたり食されるようです。

↓一方、子房がなくガクの下に茎が伸びているのが雄花。
この雄蕊には苦みがあり取り除く人もいるそうですが、わたしはこの苦みも好きです!

市場に出ることのない知る人ぞ知るこのカボチャの新芽。
オークションなどでも売られているのを見かけたりします。
結構なお値段がしますがそれも頷けます。
カボチャの新芽はさっと茹でるだけで美味しく食べることができます。

とくにからし和えは最高です!
上品な甘みと苦みが絶妙な美味しさの花付き新芽。
季節限定の貴重な味わいを堪能することができました!!

******
2025年9月29日 11:00
「腐乳(フールー)」をご存知でしょうか?
漢字だけ見るとすごい名前ですね。
豆腐を麹につけ、塩水のなかで発酵させた中国の食品で、別名は豆腐乳(ドウフールー)です。
半年ほど発酵させ、コクのある深い独特の味わいが生まれます。
豆腐を麹につけて、塩水のなかで発酵・・・
考えただけですごそうです(笑
しかしなぜかやみつきになる「腐乳」は、「東洋のチーズ」と呼ばれるほど濃厚で深い味わい、ねっとりとした食感が特徴的です。
たんぱく質が多く健康食品としても親しまれ、お酒との相性も抜群で、知る人ぞ知る夜の人気のおつまみです!
自家製でも作れますが、購入してきたものをさらに冷蔵庫で賞味期限を気にせず発酵させるのが簡単で良いと思います。
こちらは中国で購入してきたものをさらに10年ほど冷蔵庫で寝かせたもの。
正直、物凄い臭いが漂います!
しかし、これがブルーチーズのようで美味しいのです!
この「腐乳」が明から伝わり現在沖縄のソウルフードとなっているのが「豆腐よう」です。
「腐乳」にはお酒が使われていないのに対し、沖縄の「豆腐よう」には沖縄特産のお酒である泡盛や紅麹などに漬け、長時間発酵させます。
漬け汁によって色も味も変化し独特の味わいが発生します!
さらにこちらは「糟方腐乳」というもので、醤油で漬けこんでいます。
同じく、中国で購入してきたものを冷蔵庫で5年以上寝かせたものです。
上の「腐乳」よりも強烈なクセが口に広がります。
(本場中国人でも苦手な人も多いほどだとか!)
たしかに、甘いような、すっぱいような、辛いような・・
なんとも表現しがたい味わいです!
発酵食品ならではのクセがありかなり濃厚なので、つまようじでチビチビと、ほんの少しの量を舌の上にのせて口の中でゆっくりと味わうのがおいしく食べるコツです。
野菜スティックや、肉料理などほんの少しつけて食べるのも美味しいです。
こちらは唐辛子の入ったピリ辛バージョンで生野菜との相性が抜群です!

わたしはよく鶏ハムや野菜につけて食べています!
やみつきになる「腐乳」は、お酒好きな方にも、ゆっくりとお酒を飲みながらつまむにはもってこいです!
***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店でお買い求めいただけます。
ご購入は、学問の概要を掲載しております下記サイトもぜひご利用ください。
https://namigaku.com/all/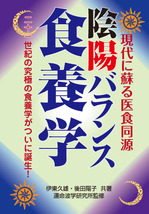
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/
2025年9月26日 11:00
9月半ばに収穫したミョウガはとても大きく、花が咲いていました!
花が咲いている状態のミョウガを初めて見ました!
このゴロンとしてまるまるっとして、ずっしりした大きさを伝えたくて何かないかと探して、とりあえず誰かのポケットにあったスイカと比べてみました!笑
 よく見るサイズと比べるとこんなに違います。
よく見るサイズと比べるとこんなに違います。

まずは洗って花を取ります。
長持ちさせるコツは、水をしっかり切ること!
洗ったら花茎の方をもって振ると結構な水が出てくるんです。
そして長い花茎は切っておきます。
(切った花茎ももちろんトッピングやお味噌汁に入れるなどしていただきます!)
料理に使ったり、また糠漬けや酢漬けなどにして、美味しくいただきました!

そしてこのミョウガの花もとても美味しいそうで、とくに三杯酢が最高とのことで早速作ってみました!

ミョウガよりも柔らかく、また味もマイルドなのにしっかりミョウガ特有の上品な風味があります。
鮮やかでキレイで本当に絶品でした!
本丸の前オーナーさんは、これまで使われていなかった地を自分たちなりに楽しく再生していくわたしたちを見て、本丸の裏手にある新たな土地を「ここも自由に使っていいよ」と無料で使わせてくれることになりました。
とてもありがたく嬉しいご厚意です。
そしてこの地にも、日陰になっている場所にミョウガの群生を発見!
やったぁ!!と思わずガッツポーズをしてしまいました!

******
2025年9月24日 11:00
わたしにとって大好きを通り越して別格の存在、ミョウガの群生が本丸にあります。
代表が自生しているミョウガを見つけてくれた時は本当に嬉しかったです!!
ミョウガの草丈は通常40cmから100cm程度と言われていますが、こちらのミョウガは生育環境がとても合っているのか、大人の身長くらいありとんでもなく大きいです!
この念願のミョウガを9月の頭(9/4)に収穫してみることになりました!
・・しかし以前、ここはわたしがブヨにやられまくった場所・・
少し近づくのをためらっていると、

男衆がそんなことはものともせず軽装でグイグイと潜り進んで収穫してくれました!

ミョウガはこんな風に生えているのですね!目の前で見たのは初めてです!!

草や枯葉の下に埋もれているので、かき分けないと分かりません。

こういうところにもあるよ、と教えていただきました。
土の中にも隠れているんですね!

たくさん獲れました!

その場で軽く洗い、軽く干してなるべく水気をなくしてから東京に持ち帰りました。

2週間後(9/18)には、さらに大きくなって花もついていました! 前回と比べてもすごく大きくなっているのが分かります。
前回と比べてもすごく大きくなっているのが分かります。
↓写真中央が2週間前の収穫時のミョウガ。 この花の部分も美味しく、特に三杯酢で食べるのが最高なのだそう!
この花の部分も美味しく、特に三杯酢で食べるのが最高なのだそう!
ミョウガの花は食べたことがないので楽しみです!
******
PAGE TOP