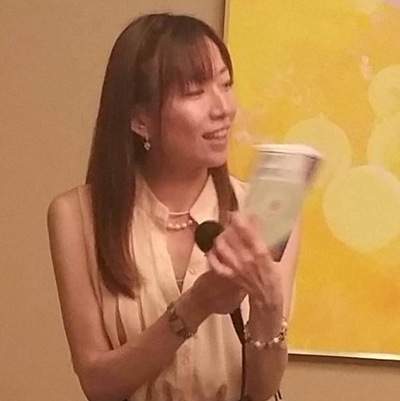4月に植えた2種のミニトマト(4/9)。
苗は購入してから日数が経っていて萎れ気味で、少し不安があったのですが元気に成長し1ヶ月半後には花を咲かせました!
 開花から二週間後には実を付けました!
開花から二週間後には実を付けました!
ミニトマトってこうやって成るんですね、知らなかったです!
 こちらは別の品種!
こちらは別の品種!

その後もみるみる大きくなります。
後ろのフェンスと比べてもその成長が分かります。
↓(5/29)の様子。

↓(6/12)の様子。
肥糧もあげてないし水も天然の雨だけです!
「だいぶ前に植えた自分たちのミニトマトよりも大きくなっている!」とご近所の方も驚いた様子で見に来ていました!
↓(6/22)の様子。
 なぜこんなに成長しているのか代表に聞くと、水はけが良いのはもちろんのこと、土より上に位置しているため、連日の猛暑日などといった地面の温度等の影響をダイレクトに受けづらいのではないか、とのことでした!
なぜこんなに成長しているのか代表に聞くと、水はけが良いのはもちろんのこと、土より上に位置しているため、連日の猛暑日などといった地面の温度等の影響をダイレクトに受けづらいのではないか、とのことでした!
やはりレイズドベッドってすごいんですね!!
早速この日は収穫してみることにしました(6/24)!


みんなで収穫しながらつまみ食いしてしまいましたが(笑、たくさん獲れました!
 この日は他に、シソ、シロザ、フキ、タンポポ、オオバコ、カボチャの新芽、スギナなどを収穫しました!
この日は他に、シソ、シロザ、フキ、タンポポ、オオバコ、カボチャの新芽、スギナなどを収穫しました!
 このミニトマトは普段スーパーで食べているものよりもとても味が濃く強くてビックリしました!!
このミニトマトは普段スーパーで食べているものよりもとても味が濃く強くてビックリしました!!
甘みもありとても美味しかったです!
今後もまた行くたびに取れるということで楽しみです!
*******
5月に本丸に畑づくりを開始しました(5/13)!。
畝を作ることから・・これ、やってみてわかりました、みなさん簡単そうにやっているように見えますが、すごくコツも力もいるし重労働なのですね!><
↓ただ土をほじほじするだけで精いっぱい・・
ぜんぜん上手くできなくて即ギブアップしてチェンジしていただきました・・
 代表と園芸のスタッフが一瞬で作ってくれました(笑。
代表と園芸のスタッフが一瞬で作ってくれました(笑。

ここには安納芋などのお芋2種を植えました!

周囲には、水ナス。

唐辛子4種(シシトウ・甘長とうがらし・鷹の爪・万願寺とうがらし)。

姫カボチャ(5/29)。

約40日後(6/22)。
刈った雑草を周囲に敷いています。
乾燥しないようにするためで、草マルチと言うそうです!

さらに、自然農は育った野菜から種がこぼれ落ちで翌年自然に芽が吹いてくることを目指しているので、勝手にこの地に定着する野菜は何かを見極めるヒントになればということで、水耕栽培の実験で余っていた10種ほどの種を適当に撒きました。
意外だったのが、元々は野草で一番放置栽培に向くと思っていたルッコラが元気がないこと!
現在売られているルッコラの種は人工的に改良されたもので、野草そのもののルッコラとはだいぶ違っているのではないかということでした。
予想と違い実際にやってみて分かることもあって、すごく面白いですね!
******
地方オフィスでの庭で姫カボチャを育てています。
↓3月下旬(2025/3/27)に植えてから1ヶ月後の姫カボチャの苗の様子。
ほとんど成長していません><

別の苗も、寒さで弱った葉は虫にやられて穴だらけになってしまいました・・

植えた後に、現地の気温がマイナスになる日もあるほど冷え込み、植える時期が早すぎたのかもしれないね、とのことでした。
このように、もしかしたら育たないかもと心配していた姫カボチャですが、その後も見守っていると枯れることなくがんばって持ちこたえてくれていました!
↓そして5月下旬(5/29)になるとて蕾がしっかり成長してくれていて嬉しかったです!

そして6月中旬(6/12)。
雑草に埋もれつつ葉も大きくなっています!

放置栽培の実験中のため手を加えていないのと、虫がカボチャの葉を食べないように、周囲に雑草をはやすことで雑草に虫が行くようにしていました。
これからは暑くなりそしてこの後雨が当面降らないので乾燥防止で刈った草を敷きました!
これをマルチングと言うそうです!

蕾の方も大きくなっています!

↑この丸い部分が付いているのが雌で、
↓ついていないこちらが雄なのだそうです!ぜんぜん知らなかったことばかりです。

そしてこの時「カボチャっていうのは、この新芽の部分が一番ウマいんだよ!」とこれまた知らなかったことを代表に教えていただきました、子供のころにおじいさんが畑でカボチャ含めいろいろなものを育てていたのだそうです。
たくさん実が採れるように摘心する芽をさっそく採取!

初めてまじまじと見たカボチャの芽。


なんだか棘みたいなのも生えていますし、見た目もごっつい。
本当に食べられるの・・?と内心半信半疑だったのですが、こちらをさっと湯通しして食べてみました。
すると、美味しすぎてびっくり!!!
あまりの美味しさに思わず美味しいと雄叫びをあげてしまいます(笑
見た目とは裏腹に、すごく柔らかくて、優しい甘みがあります!
そしてふんわりとわずかにカボチャの風味もしてきます。
この新芽が食べたくてカボチャを育てるという人もいるくらいだとか!
自身で育てていないと絶対に食べられない部分。
酢味噌につけたり天ぷらにすると最高だそうです!
農家さんの特権なのですね!
 どうしよう、またひとつこの世で美味しいものを知ってしまいました・・笑
どうしよう、またひとつこの世で美味しいものを知ってしまいました・・笑
******
甘みが強く栄養価が高いマルベリー。こちらは「桑の実」です。
桑は蚕のエサとして栽培されたもので、野生化した桑の木が里山には点在しています。
正確には、実がたくさんつくよう改良品種した桑の木をマルベリーと呼んでいます!
生の桑の実はとても傷みやすいため流通品は皆無となっているのだそう。
冷凍の桑の実は期間は限られますが通販で手に入るようです、ただ養蚕業が衰退した現在はお値段がとっても高いです・・。
生のマルベリーは甘みが強いのが特長ですが、赤い実は酸っぱすぎてビックリします!黒くなった実がとても美味しいです!
そしてマルベリーのすごいところは、その美味しさだけでなく栄養価。とくにビタミンCや鉄分が豊富で、またカリウムはフルーツの中ではトップクラスの含有量といわれています。
アントシアニンやカルシウム、マグネシウム、食物繊維なども摂取できます。
なかなか手に入らない生の桑の実を毎日食べられるのは贅沢なことなのでとてもありがたいです。
こちらを毎日食べ続けていたら、最近肌が白くなったね、と言われることが増えました!
 一般的には、赤から黒になる、と言われていますが、よく観察するともっと細かい色の変化を楽しむことができます!
一般的には、赤から黒になる、と言われていますが、よく観察するともっと細かい色の変化を楽しむことができます!
ちなみに、代表は緑・白・黄色・オレンジ・赤・紫・黒、という七色に変化することから、レインボーベリーと命名しているようです。
 東京のベランダ菜園で長らく楽しませていただいたこのマルベリーも、いよいよ本丸へお引越!自然界へデビューです!
東京のベランダ菜園で長らく楽しませていただいたこのマルベリーも、いよいよ本丸へお引越!自然界へデビューです!
どのように育つのか楽しみです。元気に大きくなりますように。
******
 開花から二週間後には実を付けました!
開花から二週間後には実を付けました! こちらは別の品種!
こちらは別の品種!


 なぜこんなに成長しているのか代表に聞くと、水はけが良いのはもちろんのこと、土より上に位置しているため、連日の猛暑日などといった地面の温度等の影響をダイレクトに受けづらいのではないか、とのことでした!
なぜこんなに成長しているのか代表に聞くと、水はけが良いのはもちろんのこと、土より上に位置しているため、連日の猛暑日などといった地面の温度等の影響をダイレクトに受けづらいのではないか、とのことでした!

 この日は他に、シソ、シロザ、フキ、タンポポ、オオバコ、カボチャの新芽、スギナなどを収穫しました!
この日は他に、シソ、シロザ、フキ、タンポポ、オオバコ、カボチャの新芽、スギナなどを収穫しました! このミニトマトは普段スーパーで食べているものよりもとても味が濃く強くてビックリしました!!
このミニトマトは普段スーパーで食べているものよりもとても味が濃く強くてビックリしました!!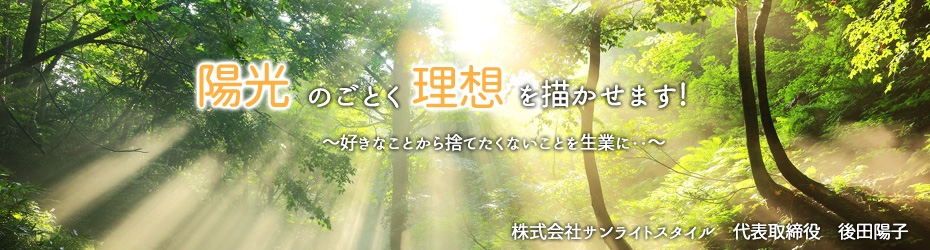
 代表と園芸のスタッフが一瞬で作ってくれました(笑。
代表と園芸のスタッフが一瞬で作ってくれました(笑。















 どうしよう、またひとつこの世で美味しいものを知ってしまいました・・笑
どうしよう、またひとつこの世で美味しいものを知ってしまいました・・笑 一般的には、赤から黒になる、と言われていますが、よく観察するともっと細かい色の変化を楽しむことができます!
一般的には、赤から黒になる、と言われていますが、よく観察するともっと細かい色の変化を楽しむことができます! 東京のベランダ菜園で長らく楽しませていただいたこのマルベリーも、いよいよ本丸へお引越!自然界へデビューです!
東京のベランダ菜園で長らく楽しませていただいたこのマルベリーも、いよいよ本丸へお引越!自然界へデビューです!