2025年11月17日 11:00
本丸の庭の枯れ木に巻き付いて成長していたブラックベリー。
景色としては良かったのですが、こちらの枯れ木はとても古くいつ倒れてもおかしくないため伐採することになり、ブラックベリーには支柱を新たに設置しました。
古木さん今までありがとう。
庭の数々の古木の伐採はほぼすべて代表と会社の男性陣で自力で行いました、重労働おつかれさまでした。
ブラックベリーもとてもいい感じです!
また来年も楽しみです。
******
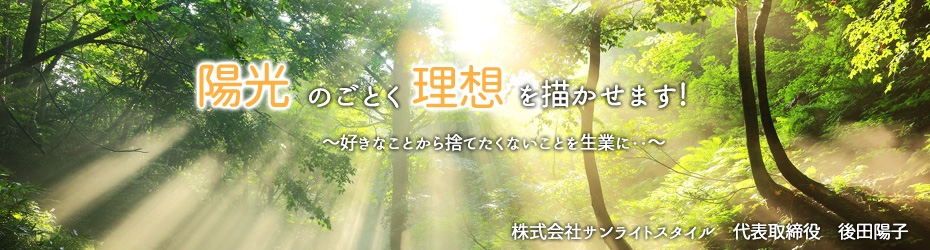
2025年11月17日 11:00
本丸の庭の枯れ木に巻き付いて成長していたブラックベリー。
景色としては良かったのですが、こちらの枯れ木はとても古くいつ倒れてもおかしくないため伐採することになり、ブラックベリーには支柱を新たに設置しました。
古木さん今までありがとう。
庭の数々の古木の伐採はほぼすべて代表と会社の男性陣で自力で行いました、重労働おつかれさまでした。
ブラックベリーもとてもいい感じです!
また来年も楽しみです。
******
2025年11月10日 11:00
ラボ内に在るスパイスラックには、100種を越えるスパイスとドライハーブ類が並びます。
インテリアにもなって良いですね。
先日も一気にスパイスやドライハーブが届きました。
世界中で使われているスパイスやハーブ類をまずは自身で一つ一つ味を覚えて日々食と健康を追求しているファンシーフーズ代表が取り寄せたもの。
わたしも一緒に勉強させてもらっています。
スパイスはハーブの種や薬効成分が豊富な草木などの種・葉・皮・根などです、したがって自然の薬効成分である身体に有益に機能するフィトケミカルが大量に詰まっています。
漢方薬の処方を見ても解るように、漢方薬のほとんどがスパイスの組み合わせによってできています。
しかし日本では食材の味を活かした優しい味付けが食文化の本流にあります、したがって味が一変してしまう癖の強いスパイス類やハーブは好まれないようです。
そこで現在、ファンシーフーズでは各種のスパイスを実際に取り入れた調理をしては方向性を見いだそうとしています。
「食べる生薬」を日本人にもっと普通にスパイスのある食生活を提案していければと考えています!
さて、ベランダ菜園では毎年恒例でローズマリー・パセリ・バジルという特徴的な香りと味のそれぞれの科目代表であるハーブを育てています。
こちらはバジル。
バジルを乾燥させたホーリーバジルやバジリコ作りもしています!
ローズマリー。
遥か昔に、海路を経て持ち込まれたスパイスはほとんどが乾燥させた植物ですが、ハーブは乾燥させたものだけでなく生鮮ハーブの形でも利用されています。
区別するために、生の状態の植物をフレッシュ+(植物名)と呼ぶのに対し、乾燥させてある植物をホーリー+(植物名)と呼ぶのだそうです。
ホーリーとは、クリスマスソングで有名なホーリーナイトのホーリーで聖なるという意味ですが、フレッシュとは逆の状態で細胞自体は生きていません、そのため静かなる植物という意味でつけられているのだそうです!
ほとんどが乾燥状態のスパイスは、本来ならばホーリー+(植物名)となるはずですが、ホーリーをつけずにそのまま植物名で呼ばれています。
種類もスパイスが数百種類程度なのに対し、ハーブの種類は万を超えるとも言われています。
スパイスとハーブの違いについでは諸説あるものの、どちらも、料理用や芳香、薬用、園芸・鑑賞用など、古くからわたしたちのあらゆる生活全般に取り入れられてきた欠かせない存在であったことが見えてきます。
厳密に定義分けをするよりも、まずは気軽に身近に取り入れて楽しんでいきたいですね!
***
2025年10月 6日 11:00
4月に植えた2種のミニトマト(4/9)。
自然農を取り入れた放置栽培を実践としてレイズドベッドに植えて約5ヶ月の間に、ものすごい量を収穫できました!
2週間おきでは収穫が間に合わないほど成長し、実が付きすぎて重さに耐えきれず枝の何本かが折れてしまうほどでした。
折れてもさらに実をどんどんつけていく姿に「肥糧無しだなんて信じられない!!」と近所の方も驚いていました!
赤くてきれい。数珠成りになっています。

こちらは長細い「純甘」という品種です。熟したものは本当に甘くスイーツのようです!

4カ月半の間に、熟しすぎたものはその場で食べたりしながら8回ほど収穫して、おそらく2,000個以上は採ることができました!
下の写真は一部です。





その後もまだまだものすごい量のミニトマトが成っていました!
次の野菜を植えるため、最後の収穫をしました。(9/4)
2週間おきの収穫のため落ちてしまった実もたくさんありますが、
最終的には1株で1,000個、都合4,000個を収穫し、レイズドベッドでの放置栽培は大成功を収めました!
今年はミニトマトを思う存分堪能できました!
それにしてもこちらの代表考案のレイズドベッドはすごい!
土の中にいる糸状菌のパワーを活かせた結果だそう、糸状菌恐るべしです!!
******
2025年9月23日 11:00
前回から2週間後に、2回目の秋の収穫祭をしました!(9/18)
この日は前回と打って変わって、気温は真夏ほどではないのですが蒸していてとても暑い日、大量の汗をかいて体力を奪われてしまいました!
この日もまずは本丸から!
果樹園の方に行くと栗がたくさん落ちていました!

 箸でつまんで、足でイガを割って取り出します!
箸でつまんで、足でイガを割って取り出します!

そしてこちらも果樹園の方で干し柿で有名な大型渋柿が成っていました。
まだ早いのですが、柿の木もまた老木のため生理落果が激しいので、未完熟実を試験的に20個ほど収穫してきました!
代表が独自方式で未完熟実の干し柿を作ってみるそうです。

こちらはとうもろこし。
夏蒔きの秋収穫を狙った実験とうもろこしですが、やはり時期が遅すぎたのかあまり成長できなかったようです!この地での夏蒔きはかなり厳しいようです!
ただ小さな割にはすごく甘く、美味しくいただきました!!
時期を間違わなければ甘くて美味しいとうもろこしができると分かり、失敗もノウハウとしてまた次に活かしていきます!

カボチャ。摘心した芽や花も!

こちらは巨大ミョウガ(花付き)。
 その他、水ナスなどを収穫しました!
その他、水ナスなどを収穫しました!
次はオフィスへ移動し、長ナスや、カボチャ、自生しているシソ(花付き)などを収穫しました!

翌日は筋肉痛のヘトヘトになり一日仕事になりませんでしたが(笑、すごく楽しかったです!
みんなで分けて美味しくいただきました!!
代表は1年を通してこの地の気候や植物環境などの自然特性がだいぶ把握できるようになり、いつ頃自生している植物がどのような状態になるのか、いつ頃それらが収穫時期を迎えるかなどかなり解ってきたそうです!
わたしもただ食べてるだけでなく(笑、もっと学ばないといけないなぁと思います!
昨年来からのこういった各種の栽培実験を通して、年間スケジュールが立てやすくなったようです、これからがますます楽しみです!
******
2025年9月22日 11:00
9月に入り、秋の収穫祭をしました!(9/4)
この日は涼しく、外の作業も気持ちが良かったです。
午前中は本丸で!
サツマイモ2種。
水ナスやカボチャ、柿、自生しているミョウガなど!
午後からはオフィスの方に移動しました。
こちらはミニトマト。
今回で最後にすべてを収穫することになりました!
大量なので大きなシートの上に、すべて丁寧に取り出してひとつひとつ収穫していきます!
途中で雨が降ってきてしまい、屋根のある場所に避難しながら。 すごい量になりました!おそらく2000個以上あります!
すごい量になりました!おそらく2000個以上あります!
まだ青いグリーントマトもどんな料理に使っても美味しく食べられます。
茶豆も収穫!
少し小ぶりでしたが美味しくいただきました!
ミニトマトと茶豆を育てていたレイズドベッドはきれいになりました。
最後は土を均して、次の植え付けのためにしばらく休ませます。 その他、長ナスやカボチャ、自生しているシソなども収穫し、楽しく身体を動かして大満足の1日でした!
その他、長ナスやカボチャ、自生しているシソなども収穫し、楽しく身体を動かして大満足の1日でした!

******
PAGE TOP