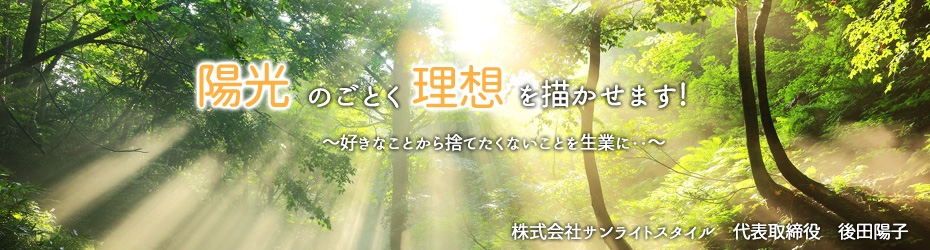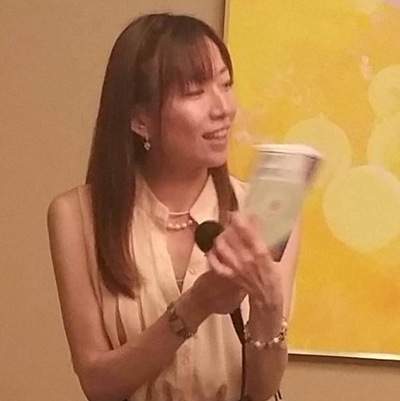タンポポの根の採取の際に大量の葉も採取できます。
そのなかに、幾つかの蕾の付いた花茎を発見、食してみることにしました!

ちなみにタンポポの種類は「西洋タンポポ」、
つまりヨーロッパでは食用とされている種です。
この西洋タンポポか日本古来の在来種タンポポかの見分け方は葉では見分けがつかず、蕾を見るのがもっとも確実です。
蕾の外側の額に反りが入っているのが西洋タンポポで、
反りが無いのがほぼ在来種ということになります。
さて、タンポポの蕾の味は?
花茎は無味、
蕾は香りの無いカモミールのようでほろ苦く意外と美味しいです。
素の味を確認するため、
調理法はオリーブオイルで素揚げ、他の調味料は何も使いません。
それなのに若干の苦みに加えて甘みがあり、
調理方法によっては下手な山菜よりもはるかに美味しい食材です!
次回は、蕾、花、種を飛ばした後の額、それぞれの状態に応じた味と食感を確認したいです。

***
ポッドで育てられ、そのまま家庭に届けてくれる生きたままのポッド野菜。
グラスなどに入れて水だけを1日少し入れてあげるだけで、2週間ほどはどんどん成長してくれます。
それは、使っている培養土に大きな秘密があります。
普通の土ではなくて、抗菌材をベースに必要な栄養素が野菜に行き渡るように工夫されています!
フルボ酸のバイオ土壌と抗菌水、そしてクリーンルームで育てられた野菜は虫も雑菌も埃もついていません。
勿論、有害物質などもない野菜本来の栄養素と酵素を充分に摂取していただけます。
そのままポッドごとグラスに入れて毎日欠かさず水をあげると、1週間は鮮度を保ったままどんどん育っていきます。
ダイニングテーブルやキッチンにおいて食べる際に必要量を摘んで食べられますので、
つねに摘みたて野菜を食べることができます。

現在、約30種類!
・レッドオーク
・レッドロメイン
・レッドパクチョイ
・ルッコラ
・レッドマスタード
・レッド水菜
・レッドケール
・ビートフラッド
・レッドスピナッチ
・アイスチャード
・チコリ(イタリアンレッド)
など!
イタリアの野菜を中心に、
世界中の珍しい特徴的な野菜で、
どれも、日本ではあまり見ることが出来ない葉野菜ばかり。
色付き系の野菜は、現代人に不足しがちなミネラルやポリフェノールが豊富です。

摘んでそのままドレッシングやオリーブオイルをつけてバーニャカウダのようにバリバリ食べています。
オフィスの窓際に置いておくと、数日で新しい葉がどんどん出てきます。

5ポッドで2回3~4人前摘んだ後でも、こんなに葉が残っています(というか増えてきます)。

適当に各種類を摘んでサラダに!

鯖サラダ。

パスタのトッピングに!

ハムとオニオンスライスを加えて、冷パスタには最高です。
本格イタリアンレストランで食べる野菜が家庭で楽しめます!

育てながらサラダなどのちょい足し野菜として利用できてとても便利です。
育てて、新鮮なものを摘んで食べられる!
お子さんの情操教育にも、とても良いですね!
***
豚肩ロース肉の焼豚(チャーシュー)をたまに作ります。
その際に、熟成の過程でできる豚脂(ラード)も同時に作り置きしています。


肉を柔らかくなるまで煮込んだら、
火を止め冷ましてから冷蔵庫で2日以上熟成します。

食べる当日に冷蔵庫から出し、上に固まっている脂を全部取ります。
そして、再度煮込んで、味を調えながら最終調理を行います。

この熟成の際に、冷蔵庫で冷やしている間に脂分が分離して固まります。
これが本天然の豚脂(ラード)です!
工場で脂身だけから作られた無味のラードと異なり、肉の旨みが詰まった美味しいラードになります。
見た目は驚きますが、天然の豚脂(ラード)は脂肪分に加えて人間に必須の貴重なビタミン類など栄養素がたくさん含まれています。
豚の肩ロースだと脂肪分が少ないので2キロでわずかこれだけしか取れません。
脂身からの加工ラードと異なり、今ヨーロッパでブームの天然の熟成ラードが5倍以上と高価なのもうなずけます。
現在ヨーロッパでは、バター代わりにこの熟成ラードをパンに付けて食べるのがブームになっているそうです。


この天然の豚脂(ラード)は、野菜炒めなどの料理にほんの微量加えるだけでものすごくコクがでます!
植物オイルに比較するとカロリーは高くなりがちですが、微量でも驚くほど料理の味に深みが出ますので料理に使用するのはほんの少しでだいじょうぶです。
冷凍すれば1年以上は日持ちしますので、ぜひ豚の煮込み料理の際に作り置きをしてみてください。
さらに、冷凍している間にも熟成されて、1年ものは、チーズのような芳醇な香りがしてきます。
ポトフなどのスープ料理に使えば、これがものすごく濃厚な深い味を出してくれます!
ベーコンを使った場合の味の比では無いですよ!
***
2カ月ほど前、契約農家さんから送っていただき、研究や実験に使いきれないダイコンを大量に漬け込んでみました。
こちら、毎日味がどんどん変わってくるので不思議です。醗酵って本当に奥が深いですね。
最初の頃は塩味が先に感じられるのですが、
2カ月経った今はメロンのような香りとさわやかな甘みが口に広がります。
日が経つにつれどんどんまろやかになっていくのがわかります。
塩をできるだけ少なくしているので、漬け汁を飲んでもしょっぱくありません。
漬け汁には多くの乳酸菌が住んでいるのですっぱいです。

作り方はとても簡単。
ダイコンを適当な大きさにカットし、塩もみして香りづけに少々のお醤油を合わせるだけです。
好みでカツオダシやトウガラシを入れても美味しいです!
こちらは一味トウガラシを若干入れています。
それを適当な容れ物に入れて冷蔵庫で熟成させます。
1週間ほどでダイコンから出た水分でダイコンが隠れるほどいっぱいになります。
糖分は何も入れていませんが、熟成されてくるとダイコンの酵素や乳酸菌で徐々に甘みと酸味が増してきます。
昔の人の知恵って本当にすごい!
冷蔵庫で保管すると何日経ってもパリパリです。
こうやって冬前に仕込んでは冬の野菜の無いときでも生の野菜を食べられたのですね!
***
「ラプシー」と呼ばれる、ネパール特産の果物から作られたジャムをいただきました。
ラプシーは原産地ではお菓子などの材料になり、ラプシーキャンディというものが有名です。

こちらがラプシーです。
ネパールやブータンの一部が主な生産地と言われています。
かなりすっぱい夏ミカンだと考えれば解りやすいですね。


ラプシーを加工する際には、皮ごとプレスして天日干しして乾かして板状にします。
これをプレスした際に出た果汁と煮込んでジャムにします。
ジャムと言っても板状のラプシーは硬くて歯が立ちません!
機械を使うのはラプシーを板状にプレスするときだけ。
あとはお母さんたちが手作業で作るところも多いのだそうです。
さて、このラプシージャムですが、ラプシー特有の酸味があり、甘くて辛くてすっぱくて、甘い梅干しにトウガラシがついたような・・
不思議な味ですがとても美味しいです。
このままでも美味しいのですが、
この甘味と酸味と辛味と塩味・・
大根と漬物にしたら合いそう!
というわけで早速挑戦!
お湯で煮込んでジャムにする前の液体状に戻します。

冷まします。

この漬け汁に大根を漬け込みます。
2日後にはしっかりと漬け上がりました!
四角いものが板状のラプシーです!

味は大正解!
大根以外にも、キュウリやニンジン、レンコンなどでも合いそうですので、
いろいろ試してみたいと思います。
こちらのラプシーのジャム漬けはビンの中で保存ができ、その間も熟成されていきます。
2年ものあいだ長く美味しく楽しむことができました!
***