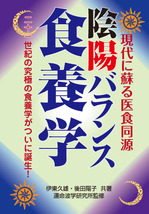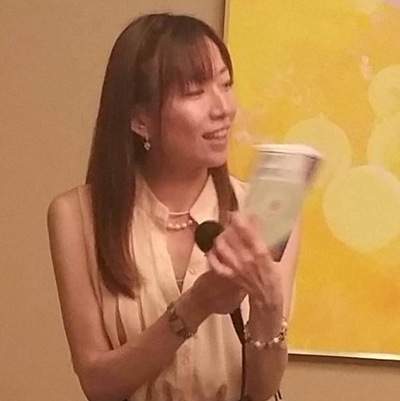卵の味噌漬けという食べ方を教えていただきました!
昔、貴重な卵を長期で保管しようと信州で考えられた作り方だそうです。
茹でた卵を味噌で漬けるのかな・・?くらいに思っていたらビックリ!
まずは生卵をそのまま冷凍庫に入れてしまいます!
生卵を冷凍したことのある方はいらっしゃるでしょうか?
解凍した卵はどうなるかというと、白身の部分だけが溶けてなくなってしまうのです。
この残った黄身を出汁味噌で漬けます。

ちなみにわたしは以前は大好きだった卵かけご飯ですが、今では若干熱を通した卵が好きで、生卵はほとんど食べなくなりました。
生卵を使った卵かけご飯は確かに手軽で美味しいのですが、数年ほど前から食後身体がダルくなるのを感じていたからです。本当に、身体が嫌がってる感じといいますか、食べたいと思えなくなったんです。
その理由がわかりました、生卵は消化に負担がかかっていたのですね。
(若いころは多少身体に負担をかけてもまったく体感として感じないんですよね・・!><)
さて、一週間ほどして完成しました!

こちらの味噌漬けは本当に美味しいです。
どれだけ美味しいかというと、卵かけご飯の「美味しい」と感じる部分だけを抽出しさらに100倍美味しくしたような味です。うまく伝えられないのですが・・笑
それでも時々あの卵かけご飯の味が恋しくなるわたしにはピッタリです!
味噌の部分は、ご飯にかけても美味しいですし、お湯で割って飲むこともできます。
昔は体調を崩したなどによく飲まれていたそうで、子供は風邪をひくとこのお湯割りが飲めるのでちょっと嬉しかったそうです。

(↑写真は、自家製のバジルを浮かべてすっきりした香りにしています。)
本当に身体がぽかぽかと温かくなるので寒い季節には欠かせなくなりました!
普段口にする醤油を自分で作ってみたいと思い、挑戦してみました!
といっても一般的な大豆から作るものではありません。
こちらは、生のショウガから発酵熟成させて作った醤油です。

こちら漬けて2週間ほどたったもの。
ここからどんどん黄金色に変化していきます。
漬けたショウガももちろん美味しく食べられます。
辛いのかと思いきや、通常の醤油と比べてもショウガ醤油はとても甘く、まろやかな味になります。
ショウガの香りは、ちょうど良い絶妙な塩梅でほのかに口のなかで香ってきます。
色も黒くないので、料理に使っても見た目に影響することがありません。
これはみんなで食べてみたのですが、想像以上の美味しさで一同衝撃の声が上がりました!

食べるときはこのように容器に移しています。
毎日醤油の代わりに調味料として食べるようになってから、身体もいつもあたたかくとても元気になりました。
ただ、作る工程は塩水に漬けるだけ、といういたってシンプルなのですが塩の塩梅が難しかったりするので、もう少し試行錯誤してみたいと思います!!
栽培しているバジルの葉を、トッピングやソースにしたり、ハーブティーにして飲んだり、芽や茎を漬け薬酒にしたりと、初夏から秋にかけて存分に楽しみました。
収穫が間に合わないほどだったため、前回はバジルの葉を使って乾燥バジルにしましたが、今回は完全に収穫を終えほぼ茎だけになったバジルを使って、より一層バジルの強い風味が楽しめる乾燥バジルを作ってみました。
作り方は簡単で、葉だけでなく最後に残ったこの茎の部分も丸ごと一緒に乾燥して作るということです。
重要なポイントは、逆さまにして乾燥させること!
 そのまま乾燥させても細胞が壊れてしまう(枯れてしまう)ので、逆さまにすることで細胞の水分だけを抜き栄養成分を留めたまま乾燥させることができるため、味がとても濃くなります。
そのまま乾燥させても細胞が壊れてしまう(枯れてしまう)ので、逆さまにすることで細胞の水分だけを抜き栄養成分を留めたまま乾燥させることができるため、味がとても濃くなります。
つまりはドライフラワーですね!
どのご家庭にもある洗濯ばさみを使えば簡単です!
完全に乾燥したら、そのまま部屋に飾って、少しずつ必要な分を都度つまんでそのまま使っています!

最後の最後まで、捨てることなくバジルを何か月にも渡って楽しむことができました!
栽培しているバジルの葉を、トッピングやソースにしたり、ハーブティーにして飲んだり、芽や茎を漬け薬酒にしたりと、初夏から秋にかけて存分に楽しみました。


香り高く、バジルに含まれるリナロールなどの香り精油成分には鎮静作用や強壮作用があり、リラックス効果があります。
ハーブと言えば独特の香りと味ですが、実はこれが自然の薬効成分であるフィトケミカルと総称して呼ばれるレアな栄養成分であり、ハーブの香り成分には、活性酸素を抑え抗ガン作用もあることも近年の研究で明らかになってきています。

バジルに含まれる脂溶性のβカロテンやビタミンE・Kは、油と組み合わせることで栄養素が溶け出し吸収率もアップさせてくれます。そのためバジルソースもおすすめです。

すさまじい勢いで成長し毎日のように大量に収穫できたので、食べきれない分は、保存食として乾燥バジルにしてみることにしました。

ちなみにバジリコとはこの乾燥バジルを細かくしたもので、日本で生まれた言葉です。
バジル粉(コ)が言いにくいのでバジリコ、となりました。
市販で売られているバジリコにはバジルの茎の部分や、他の植物も混合されているのはご存じでしょうか。
そうです、バジルの葉だけでは量がとれないためです。
完全にバジルの葉だけを使用したバジリコは、自ら乾燥バジルづくりから始めないとなかなか食べられないかもしれません。
さて、バジルを一枚一枚丁寧に干していきます。

毎日新しい葉を追加して干していきます。
乾いてきたものは色が黒っぽくなります。
 この作業を繰り返し数百枚干しました。
この作業を繰り返し数百枚干しました。
完全に乾いたら完成です!

バジルには豊富なベータカロテンをはじめ、ビタミンEやK、カリウムやカルシウムなど、強い抗酸化作用や人体の生命維持活動にかかわるさまざまな栄養成分が含まれています。
また、冒頭のリラックス効果や健胃作用もあり、季節を問わず食したい薬草です。
一年中楽しむことができる、純粋で濃厚な香りの乾燥バジル。ぜひおすすめします。
植物の生命力と古人の知恵をいただきながら
心(陰)と体(陽)の陰陽バランスを整えるお酒を楽しんでいます。
美味しくて人気のジンBombay Sapphire(ボンベイサファイア)。
最近マイブームのカクテルがこのボンベイサファイアを使ったジンバッグです。

通常はジンにジンジャーエールとレモン果汁を加えますが、本来は生のショウガとコアントローを使います。
なので、本格的なジンバックを最近楽しんでいます!
美味しいうえに、生ショウガの薬効効果も期待できます!

***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店及びAmazon・楽天等の通販書店でお買い求めいただけます。
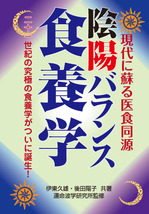
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/




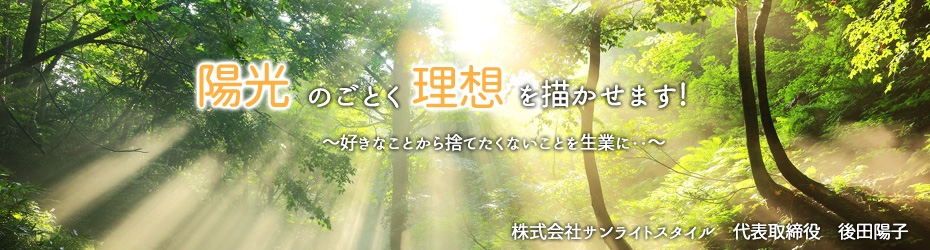


 そのまま乾燥させても細胞が壊れてしまう(枯れてしまう)ので、逆さまにすることで細胞の水分だけを抜き栄養成分を留めたまま乾燥させることができるため、味がとても濃くなります。
そのまま乾燥させても細胞が壊れてしまう(枯れてしまう)ので、逆さまにすることで細胞の水分だけを抜き栄養成分を留めたまま乾燥させることができるため、味がとても濃くなります。






 この作業を繰り返し数百枚干しました。
この作業を繰り返し数百枚干しました。