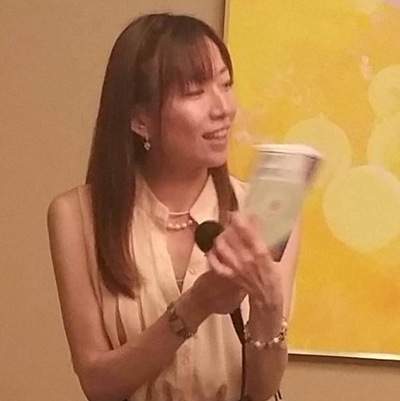日常に野草を取り入れて楽しんでいます。
ドクダミの葉や茎を乾燥させたものは「十薬(じゅうやく)」という生薬として古くから活用されてきた万能薬で、ゲンノショウコ、センブリと並ぶ『日本の三大薬草』と言われています。
日本全国各地の比較的湿った半日陰地に生息していて、よく見かける野草のひとつです。
ミネラル、ビタミン、フラボノイドを含み、利尿作用、動脈硬化の予防、解熱や解毒など数多くの効果があると言われています。
また、美容効果、デトックス効果など女性に嬉しい効果も知られています。
そんなドクダミですが、生で食すと特有の臭みとアルカロイドも強いのでおすすめできません。
やはり摂取するのに良いのはお茶です!
お茶に使うドクダミは、花が咲く前よりも咲いているものが成分も強くておすすめです。
お茶作りは基本的に干すだけなので特別なことはないのですが、とにかく、野草は洗うのが一番たいへんです・・
3日かけて大量のドクダミを洗いました!

あとは干すだけです!


梅雨~夏の時期は乾かすのに時間がかかります。
しっかり乾かすなら2週間くらいかかります。

乾いたものを、細かくして完成です。
入れ物に入れるときは、通気の良いカゴに入れると良いです!
こちらは100均に売っているカゴです。
 お湯で3分以上しっかり煎じます。
お湯で3分以上しっかり煎じます。
生でかじると相当味のきついドクダミも、お茶にするとまろやかな甘みが出て美味しいです。

このドクダミが良く咲く季節に一気に作り、密閉容器に入れて一年分作り置きしています。

ドクダミの薬効成分は化粧水、入浴剤、天然の虫よけスプレーなどとしても使えるそうなので、今後もいろいろチャレンジしてみたいと思います!
***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店及びAmazon・楽天等の通販書店でお買い求めいただけます。
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/

地元の友人と今でもときどき会って遊びにいきます。
起業後もずっと応援してくれていて、さらには当時からわたしが食べることが大好きなのを知っているので、会うたびいつもいろいろな食材をくれるのです(笑)
本当にありがたいです。
今回は北海道産の貴重なお豆をおすそ分けしていただきました!

こちらは金時豆(左)と小豆(右)。
見た目は似ていますが、金時豆は小豆と全く違う種類の豆なんです!

金時豆は「インゲンマメ属」で種皮が赤いいんげん豆の総称。
非常に赤紫色が鮮やかなことから、金時豆ではなく赤いんげん豆とも呼ばれたりします。
金時豆はいんげん豆の中でも特に代表的な銘柄で北海道で主に栽培されています。
粒の形がきれいで味わいも良いことから甘納豆の原料として使われることが一般的です。
一方で小豆は金時豆とは違い1年草の種子です。
日本における小豆の生産は北海道が総生産量の4分の3を占めています。
ちなみに、日本産のあずきは「大納言」「中納言」「白小豆」「黒小豆」の4品種あります。
お次は紫花豆。

紫花豆も「インゲンマメ属」の仲間で「ベニバナインゲン」というそうです!
キレイな花を咲かせることから花豆の愛称で知られ、甘味のある煮豆は正月のおせち料理でもおなじみですよね。
食物繊維や鉄分、カリウムやナイアシンなどの栄養素も豊富なのが嬉しいです。
今回は煮豆にしていただきました!
北海道産の紫花豆は長野県産よりは小さいサイズですが、大粒で食べごたえのに加えコクがあってしっかりとした豆の美味しさを感じます。
本当に甘くて美味しい豆でした。
次は甘納豆に挑戦してみようとおもいます。
紫花豆は非常にデリケートなお豆のため、生産量も多くなく、また毎年生産量はばらばらなのだそうです。
貴重なお豆、ありがたいです。
お次はパンダ豆。初めて見ました!

こちらも「インゲンマメ属」の仲間で北海道の在来種なのだそうです。
このパンダ豆も一般市場には出回らない貴重な豆です。
なんと北海道でも一部の農家しか栽培されていない豆なのだとか。
煮豆にすると薄茶色に変わり、ほくほくとして本当に美味しいです!
煮豆にしたり、サラダにしたり、ご飯で炊いたりと、本当に美味しくいただきました。

他にも大豆や黒大豆など、美味しくいただきました。
北海道産の豆は、旨味や甘味がしっかりとあります。
追々、陰陽バランス食の実践ブログでご紹介していきたいと思います。
***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店でお買い求めいただけます。
ご購入は、学問の概要を掲載しております下記サイトもぜひご利用ください。
https://namigaku.com/all/
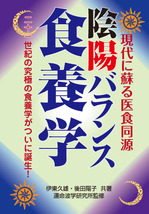
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/

陰陽バランス食養学の実践を日々楽しんでいます。
先日、大量にいただいたパクチー。
もちろん根っこは捨てずに取っておきました!
パクチーのすごい栄養と美容効果は言わずと知れたところ。
このすごいパクチーは、
じつは根も茎も葉も捨てるとこなしのハーブなのです!
スーパーでは、葉だけパックにして売られていることも多いのですが、
茎はもちろん、根っこも活用できます。
エスニックの飲食店のオーナーに伺いましたところ、
タイなどではスープストックにしたり、
調味料にしたり、肉料理などの隠し味にしたりと、
むしろ根をメインに食材として活用しているそうです!
今回は調理には使わずにまずは漬けて薬膳酒にしてみました!

これまでの薬膳酒づくりでは、収穫後水洗いして干していましたが、
今回は干す前に冷凍保存させてみたのです。
それは、冷凍することによって、
細胞が壊れて養分が出やすくするためです!
こうすることによって、薬膳酒にするときに早く熟成すると考えたからです!
冷凍した後、水分をとって天日干し。
 乾燥してきました。
乾燥してきました。

5日後、からからに!
 これを、35度のリカーで焼酎漬けに!
これを、35度のリカーで焼酎漬けに!

1ヶ月後に試飲。
甘くて、香りはパクチーそのものです!
冷凍後に乾燥させると、
甘さが増しておいしいです!
またひとつ、テクニックを覚えました!
***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店でお買い求めいただけます。
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/

ファンシーフーズでは、
お店でおつまみや食材として有効に使えるこれまでにない食材のオリジナルのドライフーズを考案中です。
本日ご紹介するのは、栄養価がトップクラスのこちらの野菜たち!
さらに栄養が凝縮されたらどんなヘルシーな食材になるんだろう。
所狭しと並ぶ多肉植物のすきまで天日乾燥させます!

こちらはビーツ。
はたして水で戻して、生のように食材として使えるのか実験に使います。

こちらは、どの部分が適しているのかを研究するため、部位別にしたもの。
輪切りも渦巻いてかわいい。

こちらはヤーコン。
ヤーコンはカットするとミネラルですぐ深い青緑になります。
これだけで中程度のヤーコンを3本使っています。

太陽光でカラカラになるまでしっかり干して熟成させました。

ヤーコンは、大成功!
熟成された自然の甘みはこのままで食べても本当に美味しいです!
オリゴ糖がビッシリ詰まったヤーコンのドライフーズ、
原価が高いので手軽なおつまみには向きませんが、
トッピングや何かの隠し味で使うのだそう。
ビーツは、これから本格的な各種の実験に入ります!
陰の野菜類も乾燥させると陰が抜けます。
乾燥させた野菜は甘みが増して陰陽バランスが調います!
***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店及びAmazon・楽天等の通販書店でお買い求めいただけます。
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/

植物の生命力と古人の知恵をいただきながら
心(陰)と体(陽)の陰陽バランスを整えるお酒を楽しんでいます。
キャットニップは、猫好きな人ならばご存知の方もいらっしゃることでしょう。
猫が好むハッカの香りに似たハーブで、シソ科の多年草です。
別名でセイヨウマタタビ、イヌハッカとも呼ばれています!

あっという間にぐんぐん成長していきます!

普段ミントティーとしていただいています。
とてもさっぱりして美味しいです。

まだまだ大量に収穫できそうなので、薬膳酒も作ってみることにしました!
まずは乾燥させるためベランダで干します。

室内でも。
 カラカラに乾燥させてビンに詰め、リカーを入れます・・
カラカラに乾燥させてビンに詰め、リカーを入れます・・

2か月後☆
たくさんのキャットニップ酒の出来あがり!


あれからさらに5年が経ちました!
写真を比べても分かるように、最初の方はまだキャットニップがリカーに浮かんでいましたが、現在は完全に沈んでいます。
味は、熟成されてどんどんまろやかに甘くなっています。
驚くことに梅酒に似た味がします!
夏は冷やして飲んでいます。
ほのかな甘みとミントならではの爽やかさがとっても美味しいです!
リカーに漬けるだけ、とても簡単で美味しいので夏にもおすすめの薬酒です!

***
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。
陰陽バランス食養学は、全国の書店及びAmazon・楽天等の通販書店でお買い求めいただけます。
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/





 お湯で3分以上しっかり煎じます。
お湯で3分以上しっかり煎じます。

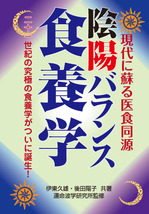

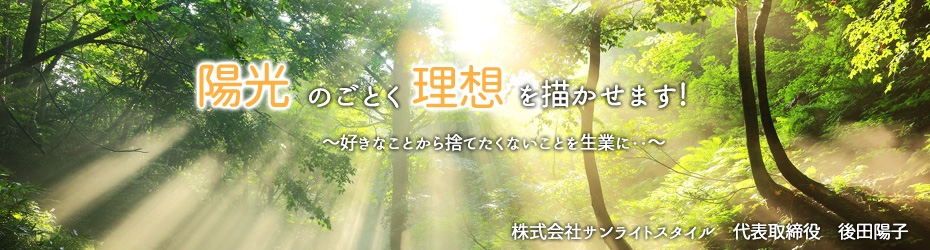






 乾燥してきました。
乾燥してきました。
 これを、35度のリカーで焼酎漬けに!
これを、35度のリカーで焼酎漬けに!
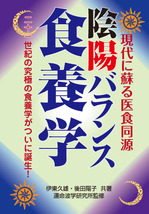










 カラカラに乾燥させてビンに詰め、リカーを入れます・・
カラカラに乾燥させてビンに詰め、リカーを入れます・・