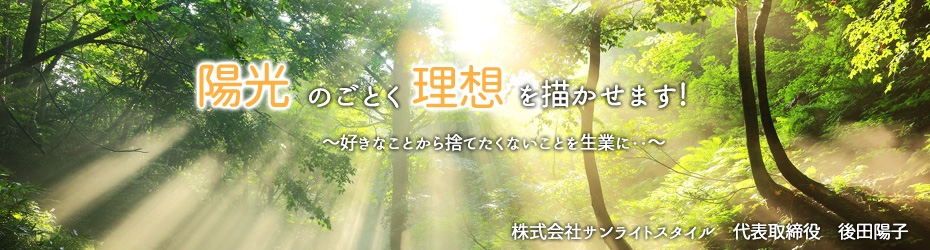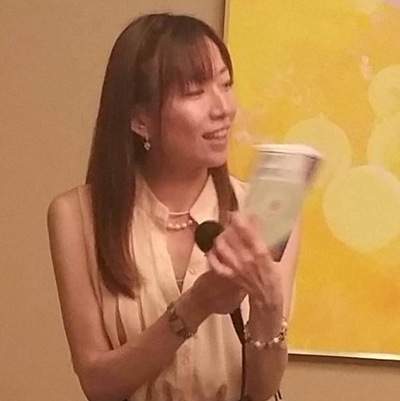お仕事仲間がご実家で育てている新米をたくさん分けてくださいます。
とてもありがたいです。

いつもは精米までお願いしていたのですが、糠漬けを作っているので玄米のままでいただき精米機を購入して糠を取ることにしました。
小ぶりな精米機ですが、食べる都度精米しますのでちょうどいい大きさです!

糠がたくさん取れます。

この糠を使って糠床にします。
塩だけでも十分に美味しい糠漬けができますが、昆布や煮干しなどを入れて出汁を効かせたり唐辛子を入れて少しピリ辛にしたりして楽しんでいます!

糠床は市販でも売られていてとても手頃ですが、添加物なども入っていることが多く、また好みの味にできるので手作りの方が自分には合っているようです!
******
とても甘くておいしいアブラナ科のかき菜。
あまり聞きなれない野菜ではないので食べたことがないという方もいるかもしれません。わたしもその一人でした!
かき菜とは小型の小松菜のような葉野菜で育つごとに次々と掻くように幼苗を摘んでいくところから命名された改良品種です。
冬前に種蒔きして間引きする感じで幼苗を収穫しながら冬越しさせ春に花茎を最終収穫するという葉野菜です!
種蒔きから約1か月後のかき菜(11/6)
小さくてかわいい葉が出てきました!
よく見ないと雑草と区別がつきません!

そこからさらに約1か月後。
青々と成長しました!(12/2)


たくさん成長してきたので幼苗の間引きをすることにしました!(12/2)

その場で洗っていただきます!
幼苗なのでとても柔らかく、そのまま生で食べてもとても美味しく本当に驚きました!
砂糖が入ってるの??!と思ってしまうほど甘かったです!
それもそのはず、かき菜は厳しい冬の寒さの中で育ち、霜に当たることで甘みを増しつつ春を迎えるたくましい野菜。
栄養も豊富で、ビタミンやミネラルはもちろんカルシウムやビタミンC、鉄分や葉酸もトップクラスだそうです!
ところで、この地は夜や朝方は冷えて氷点下になります。氷点下では植物は凍って腐ってしまいそうです。
かき菜はなぜこんなにも青々と成長し、腐らないのでしょうか?
ふと疑問に思い代表に聞いてみると、それはかき菜に含まれる豊富なミネラルにあるそうです!
不揮発性の物質(ミネラルなど)が溶け込むと、その濃度に応じ凝固点が下がる「凝固点降下」という現象が起こります。
つまり、それだけかき菜はミネラルが豊富だということなのですね!
越冬させ成長したかき菜の花茎は菜の花のような味がするそうで、春もとても楽しみです!
******
本丸の庭の枯れ木に巻き付いて成長していたブラックベリー。

景色としては良かったのですが、こちらの枯れ木はとても古くいつ倒れてもおかしくないため伐採することになり、ブラックベリーには支柱を新たに設置しました。

古木さん今までありがとう。
庭の数々の古木の伐採はほぼすべて代表と会社の男性陣で自力で行いました、重労働おつかれさまでした。

ブラックベリーもとてもいい感じです!
また来年も楽しみです。

******
ラボ内に在るスパイスラックには、100種を越えるスパイスとドライハーブ類が並びます。
インテリアにもなって良いですね。

先日も一気にスパイスやドライハーブが届きました。
世界中で使われているスパイスやハーブ類をまずは自身で一つ一つ味を覚えて日々食と健康を追求しているファンシーフーズ代表が取り寄せたもの。
わたしも一緒に勉強させてもらっています。

スパイスはハーブの種や薬効成分が豊富な草木などの種・葉・皮・根などです、したがって自然の薬効成分である身体に有益に機能するフィトケミカルが大量に詰まっています。
漢方薬の処方を見ても解るように、漢方薬のほとんどがスパイスの組み合わせによってできています。

しかし日本では食材の味を活かした優しい味付けが食文化の本流にあります、したがって味が一変してしまう癖の強いスパイス類やハーブは好まれないようです。
そこで現在、ファンシーフーズでは各種のスパイスを実際に取り入れた調理をしては方向性を見いだそうとしています。
「食べる生薬」を日本人にもっと普通にスパイスのある食生活を提案していければと考えています!
さて、ベランダ菜園では毎年恒例でローズマリー・パセリ・バジルという特徴的な香りと味のそれぞれの科目代表であるハーブを育てています。
こちらはバジル。
バジルを乾燥させたホーリーバジルやバジリコ作りもしています!

ローズマリー。
遥か昔に、海路を経て持ち込まれたスパイスはほとんどが乾燥させた植物ですが、ハーブは乾燥させたものだけでなく生鮮ハーブの形でも利用されています。
区別するために、生の状態の植物をフレッシュ+(植物名)と呼ぶのに対し、乾燥させてある植物をホーリー+(植物名)と呼ぶのだそうです。
ホーリーとは、クリスマスソングで有名なホーリーナイトのホーリーで聖なるという意味ですが、フレッシュとは逆の状態で細胞自体は生きていません、そのため静かなる植物という意味でつけられているのだそうです!
ほとんどが乾燥状態のスパイスは、本来ならばホーリー+(植物名)となるはずですが、ホーリーをつけずにそのまま植物名で呼ばれています。
種類もスパイスが数百種類程度なのに対し、ハーブの種類は万を超えるとも言われています。
スパイスとハーブの違いについでは諸説あるものの、どちらも、料理用や芳香、薬用、園芸・鑑賞用など、古くからわたしたちのあらゆる生活全般に取り入れられてきた欠かせない存在であったことが見えてきます。
厳密に定義分けをするよりも、まずは気軽に身近に取り入れて楽しんでいきたいですね!
***
ときどき薬酒の試飲を楽しんでいます。
中身を見ずに、味だけで何を漬けているのか当てるのが毎回楽しいです。
古いものは漬けて8年ほど経ちます、そのためとても甘くなっています。
比較的新しい薬酒はまだお酒の味が尖っていますが、中に漬けているものの味もしっかりするためこちらもとても美味しいです。

中でも最近でみんなに好評だったのがこちらの柿酒です。
写真右が柿酒で、左が柿茶です。

柿の実や皮に含まれる栄養素は誰もが知るところだと思います。
とても美味しくいただきました!
***