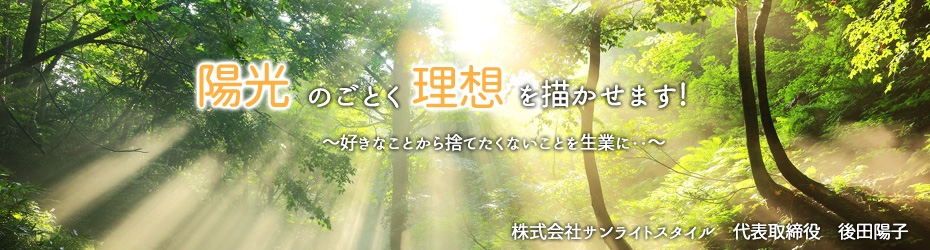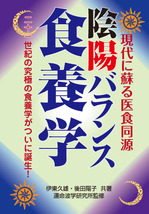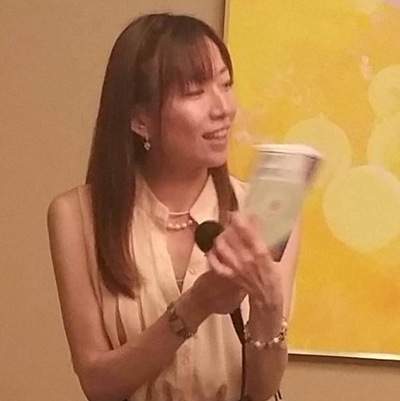2024年2月 5日 11:00
植物の生命力と古人の知恵をいただきながら
心(陰)と体(陽)の陰陽バランスを整えるお酒を楽しんでいます。
提携農家さん直送のヤーコン。
ヤーコンをご存知でしょうか?
ヤーコンとはアンデス原産の根っこがサツマイモのように大きくなる1年生の植物。
現在、日本ではまだ栽培する農家が少なく研究段階にある植物。
なのでまだ高価ですが、栄養満点な薬効植物なのです。
サツマイモのようにこの根っこを植えても生長点が無いので芽は出ません。
あくまでも養分を蓄えるだけの根っこです。

ジューシーでカットすると瞬間に、
鉄分やマグネシウムなどのミネラルで表面が黒ずんだグリーンになります!
特に皮に近いところにもの凄い量のミネラルがあるのです。
これ実は各種の実験で発見したんです!
なのでむしろ皮の方が薬効成分が豊富なんです。
ヤーコンをそのまま食べても美味しいのですが、
お酒好きのわたしたちは
ヤーコン酒にしてみました。
皮のみだとわずか数時間でミネラルで美しいグリーンに変わります。
最初は紫、次にブルー、次にグリーン、そして最後には真っ黒になります。 わずか2時間後には・・
わずか2時間後には・・
グラデーションがすごくキレイです!!

ヤーコンの皮を漬けはじめて2週間後、みんなで試飲です!
天然のオリゴ糖がたっぷりで、腸でビフィズス菌を活性化させます。
そして、自然の甘みが美味しいです!
栄養素は植物界トップクラス!
まさに生薬のキングです!
***
陰陽バランス食養学は、全国の書店でお買い求めいただけます。
陰陽バランス食養学~現代に蘇る医食同源~
「陰陽バランス食養学」は食品や調理法を陰陽スコアに置き換え、
その合計点をみれば誰でも簡単に陰陽バランスが取れているかが解るという学問。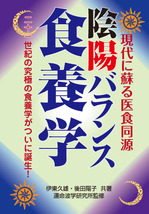
陰陽バランス食養学
https://function5.biz/youkei/