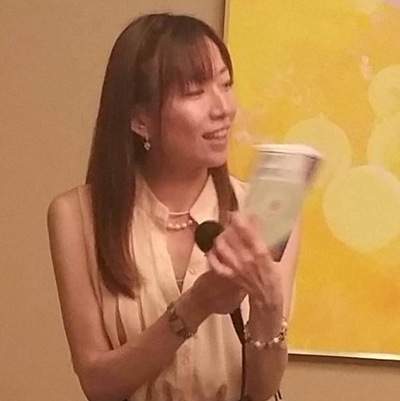本丸の庭に樹齢100年はあるかという大きな柿の木があります、低く見積もっても10メートル以上はあります!
この巨大柿の老木は手の届かないところに実を付け、これが自然落下し発酵で独特の匂いを発します、庭が汚れるだけではなく野生動物を呼んでしまう可能性もあるということで、伐採をすることになりました。
何人かの専門家に見積もりを出してもらいましたが、いろいろな伐採方法があるのですね!
結果、廃棄してしまうのに抵抗感があったため再利用ができるようプロの山師さんに根元から一発でバッサリと切ってもらい、その後のカットだけを行ってもらうことになりました!
伐採の前に根元にお酒と塩を撒いて地神の許しを得てお清めします。

倒したい方向の逆側に重心が傾いているとのことで、梯子で登りロープをかけてハンドジャッキで引っ張ります。


大きなチェーンソーで根本の一部を切ったり、楔を打ったりして、重心の調節など切っていくための前作業をしていきます。


途中ハンドジャッキが壊れてしまい、急遽新品のステンレスロープとハンドジャッキを追加して・・と予想しないトラブルが発生しましたが、すぐに対応しながらこれらの工程を手際のよくこなしていく見事なお仕事ぶりについつい見入ってしまいます!


さぁ、準備が整いました!
ここから一気に切っていきます。
チェンソーの大きな音と共に、幹が次第にミシミシと音を立てながら傾いていくのを、ドキドキしながら見守ります。

そして倒れる瞬間!ドスーンという大きな地響きと共に地面が揺れました!
想像以上の大迫力の瞬間でした!!
動画でもしっかり記録に残しました!

そしてものの見事にここしかないというスペースにぴったり倒してくださいました!
巨木伐採のプロである山師さんのお仕事を間近で見ることができ、貴重な体験ができました!

******
とても甘くておいしいアブラナ科のかき菜。
あまり聞きなれない野菜ではないので食べたことがないという方もいるかもしれません。わたしもその一人でした!
かき菜とは小型の小松菜のような葉野菜で育つごとに次々と掻くように幼苗を摘んでいくところから命名された改良品種です。
冬前に種蒔きして間引きする感じで幼苗を収穫しながら冬越しさせ春に花茎を最終収穫するという葉野菜です!
種蒔きから約1か月後のかき菜(11/6)
小さくてかわいい葉が出てきました!
よく見ないと雑草と区別がつきません!

そこからさらに約1か月後。
青々と成長しました!(12/2)


たくさん成長してきたので幼苗の間引きをすることにしました!(12/2)

その場で洗っていただきます!
幼苗なのでとても柔らかく、そのまま生で食べてもとても美味しく本当に驚きました!
砂糖が入ってるの??!と思ってしまうほど甘かったです!
それもそのはず、かき菜は厳しい冬の寒さの中で育ち、霜に当たることで甘みを増しつつ春を迎えるたくましい野菜。
栄養も豊富で、ビタミンやミネラルはもちろんカルシウムやビタミンC、鉄分や葉酸もトップクラスだそうです!
ところで、この地は夜や朝方は冷えて氷点下になります。氷点下では植物は凍って腐ってしまいそうです。
かき菜はなぜこんなにも青々と成長し、腐らないのでしょうか?
ふと疑問に思い代表に聞いてみると、それはかき菜に含まれる豊富なミネラルにあるそうです!
不揮発性の物質(ミネラルなど)が溶け込むと、その濃度に応じ凝固点が下がる「凝固点降下」という現象が起こります。
つまり、それだけかき菜はミネラルが豊富だということなのですね!
越冬させ成長したかき菜の花茎は菜の花のような味がするそうで、春もとても楽しみです!
******
いつか理想郷を手に入れたら東屋を庭に建てたいと考えていたという代表。
そんななか、地方オフィスから車で数分のところに住んでいる大工さんが、数年前に趣味で作った東屋の嫁ぎ先を探しているというお話が入りました!
現在では木材が急騰していることもありなかなかのお値段がするものです。
しかし趣味で作ったものなので材料費に若干の手数料を貰えればよいということだったのです。
とてもありがたいですね。
早々に見に行ったのですが代表は見るなり即決してしまいました!

趣味で作ったということですが、とても腕のよい大工さんだそうで、非常によく考えられた構造をしているのだそうです!

しかも天板は分厚いケヤキの一枚物でこれだけでも買えば20万円近くはする代物なのだとか。
他の木材はヒノキとスギ、屋根は伝統のヒノキの皮葺き。

しかも決めたその日に運んでいただいて設置、ということになりました。
設置作業中、近所の方々や通りすがりの人たちが見物に来ていました!笑
念願の東屋をあれよあれよという間に手に入れることができ、出会いが新たな出会いを呼ぶこと、地域の和の力を実感しました。
ヒノキの皮葺きの屋根がとても風情があり素敵。

庭の風景はだいぶ変わりました!
↓こちらは以前の庭の様子。
藤棚や大きな木がたくさん植えてありました。
物置や物干し竿、花壇など、生活感もあります。

↓現在の様子。
当時の記録が上の写真しかないため、角度など限りなく寄せて撮影してみました!

丸1年かかり今年の初夏にすべての工事が完了、と思った瞬間にどんどん追加工事がされていきます。
このあと庭には長い軒先の工事も追加される予定です!
「完成は衰退の始まり」が信条の代表、きっと永遠に完成することはない、完成までの道のりを楽しんでいるのでしょう!
わたしたちも便乗して今後も楽しませてもらいたいと思います!
******
9月に収穫した、まだ青く硬い未熟な渋柿。(9/18)
生理落下が激しかったため、このままではほとんど無駄にしてしまうのはせっかくの柿たちがかわいそうなので、まだ木に成っていた青柿を収穫しました!

これらの食べられない柿たちをどうするか・・
まだ残暑の残る9月は干し柿作りには適しませんし、しかもまだ青い未熟な渋柿・・という状況ですが、干さずに干し柿と同じ原理を再現できないか試してみることにしてみました!
渋柿が渋いのは、タンニンが含まれているからです。
しかしこのタンニンは甘柿にも含まれています。
タンニンには水溶性と不溶性があり、甘柿に含まれるタンニンは不溶性のため口のなかでタンニンが溶け出すことがなく渋みを感じまぜん。
一方、渋柿のタンニンは水溶性なので、口に入れた瞬間から溶け出してあの強烈な渋みを感じます。
しかも意外なことに糖分は甘柿より渋柿の方が多いともいわれています!
水溶性タンニンに邪魔されて豊富な糖分を感じられない状態の柿が渋柿です。
よく渋を抜くといいますが「抜く」という表現が少し誤解を招いているようで、渋=タンニンを抜いている抜けるわけではありません。
「渋を抜く=水溶性タンニンを不溶性タンニンに変化させる」
ということなのです。
面白いですね!

渋柿を甘くする方法として最もメジャーなのが干し柿かと思います!
しかし、まだ9月で気温が高かったこと、そして東京のオフィスでは外に干すことができなかったので室内で干してみてもまだ湿気も多いこの季節、熟成できないままカビてしまうものが多くありました。
それはそうかもしれません、そもそも青い渋柿を甘柿にすることは通常はしませんし・・
そこで失敗すればただでは転ばない&燃えてくる代表は、別の方法を実験してみたくなったそう。
まずは水溶性タンニンから不溶性タンニンに変化させるということで化学式を比べてみたところ、すると要はHを抜けばいいんだというシンプルな原理が分かったそうです。
カビないように腐らせないようにHを抜きながらまだ青い果肉の熟度を進ませていく、ということです。
干し柿は干すことでまさにこれと同じようなことをしていたのですね!
さて、そのシンプルな原理というのは分かったのですが、それをどうやってやるのかがわたしにはシンプルに分からない(笑)
すると、皮をむいて並べてある場所で保存するだけだったのです。
なんという簡単な方法なのでしょうか。
皮をむくのは乾燥・甘み・食感・保存性、すべてを良くするため。干し柿にする時と同じです!

途中経過。
青く硬かった渋柿が柔らかくオレンジに熟成していきます。
 ↓ちなみにこちらは大きめにカットしたものですが、やはり小さめに切った方が熟度の進みは早いです。
↓ちなみにこちらは大きめにカットしたものですが、やはり小さめに切った方が熟度の進みは早いです。

↓わずか2週間ほどで完成しました!
水溶性タンニンが不溶性タンニンに変化した結果、とても甘くなっています!
一般的な干し柿と違うところは食感です。
よくわたしたちの口にしている干し柿は全体的に柔らかいですが、こちらは中はしっとりと柔らかのですが、外側はコリコリとしているので、新しい食感の干し柿になりました!
これで食べられなかった青柿たちも無駄にすることなく美味しく食べることができました!

ただなかには、数個だけ熟度が進まないまま干からびてしまったものもあったため、具体的なやり方は100%うまく行くような方法が整ってからお伝えしたいと思います!
その他にも、アルコールでも水溶性タンニンを不溶性に変化させることができますので、梅酒を使ってジャムにしてみようと思います!
******
本丸の庭に3本の柿の木があります。
どれも大きく、それぞれ5メートル、7メートル、15メートルを超える高さです!
そのうち1本は甲州百目。
甲州百目は渋柿の一種でそのまま生で食べることはできませんが、干し柿にすると糖度が高くなり甘く美味しくなります!

↓7月頭の様子(7/5)。
小さい実が成っています。


↓9月の半ば(9/18)。
大きくなりました!
実は釣鐘のような形をした大きな品種で一般的なもので300g〜400g、大きいものだと500g以上になることもあります。

本来は10月下旬から11月にかけて収穫される甲州百目。
この時まだまだ青く収穫には早かったのですが、生理落下が激しくほとんど落ちてしまっていたため、急遽獲ってしまうことになりました。
4メートルの巨大梯子を使って上の方に成っている実を獲りますが、それでも7メートル以上あるこちらの木。届かないものは諦めます。


そしてこの青柿を無駄にしないよう、甘柿にできるか実験&チャレンジしてみることになりました!
通常、まだ青い渋柿を収穫して甘くするということはありません、本来なら熟成してオレンジになった渋柿を収穫し、渋を抜いていきます。
木に成っている状態でないとこのまま熟成せずに悪くなってしまいます、果たしてうまく行くのでしょうか。
また、渋柿は干し柿にして渋を抜いていくのが一般的ですが、代表には他に考えていた方法があるそうでこれを機に試してみるそうです。
というのも、以前干し柿にしてみた(他の柿の木に成っていた)柿は、まだ9月で気温が高かったこと、そして東京のオフィスでは外に干すことができなかったので室内では湿気が多くカビてしまい失敗してしまいました。
さらに最近の気候の変化で柿が早期に熟してしまい、これまでよりも収穫期が早まったことで干し柿作りの季節も早まってしまい、干し柿作りには適さないまだ暖かい気温ではカビの原因になったりするため、従来の方法での干し柿作りが近年では難しくなりつつあるとの話も聞きました。
そこで今回は干す以外の方法で渋柿を甘柿にする実験してみようと策を練っていたということなのです。
これがうまく行けば、干し柿作りが難しくなっている現在でも素晴らしい対策になるかもしれません!
******










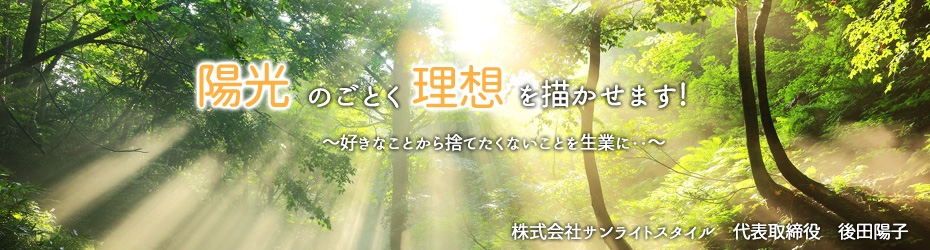













 ↓ちなみにこちらは大きめにカットしたものですが、やはり小さめに切った方が熟度の進みは早いです。
↓ちなみにこちらは大きめにカットしたものですが、やはり小さめに切った方が熟度の進みは早いです。