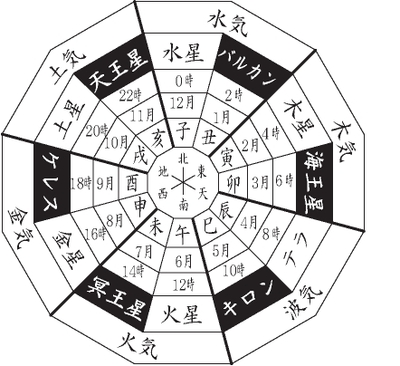「運命波学」基礎理論誕生秘話-3(「4+2=6」法則の検証③)
2025年5月15日 07:00
「4+2=6」元素による「改訂五行思想」(後の「運命波学」)ですが、この符号を元に調査・検証の結果、生命の基本であるDNAと栄養素は見事に一致していました。
そこで、基本的なことを忘れていることに気が付きました。
「五行」と言えば「色」です、五行では「木・火・土・金・水」に対して、それぞれ「青・赤・黄・白・黒」を割り当てています。
これらの色を科学的に分割すると、青・赤・黄は光の波長による色彩であり、色の構成要素となります。
また、白・黒は全ての波長の光の「反射」(白)と、同じく「吸収」(黒)という要素の色です、したがって補助要素と言えます。
従って、「五行思想」の色は「構成要素3+補助要素2」となります。
では、「改訂五行思想」(「運命波学」)を考えた場合、残りの構成要素であるもう一つの色とは何色なのでしょうかか?
皆さんの頭にはきっと「緑」が浮かんでいると思います、私も「緑」だとして検証してみました。
あくまでも、思い付きでは駄目なのです、「学問j」と言えるのであれば科学的な根拠を見出さなければなりません。
まず、「色の三原色」を調べます。
光として直接目に入る場合の三原色はテレビやデジタルカメラの映像素子、そして人間の色彩細胞も「赤・緑・青」の3色です。
黄色は赤と緑によって合成で生まれます。
また、インクや絵の具など白い紙などの媒体に塗った場合は、光は反射して間接的に目に入ります。
この場合は、上記の「三原色」とは異なり、「赤・黄・青」の3色になります。
ここで「原色」の定義は、他のどの色を混ぜても生まれない色と言うことです。
と言うことは、直接の場合の光の三原色の「黄」、インクや絵の具での間接の場合の「緑」は、それぞれ合成で生まれるので原色では無いとされているのです。
では、「五行」の「黄」は間接視覚によるものなのでしょうか?
科学的検証として、色分布の光の中心波長(一つの波の長さ)を調べてみました。
・赤=700nm(ナノミリメートル)
・黄=600nm
・緑=520nm
・青=460nm
と、以上のように緑と赤の間にはかなりの差があることが判ります、そこを黄が埋めるように存在しています。
実際にテレビやLED(発光素子)などでは赤・緑・青の3色による発色では綺麗な黄色は出すことが難しいようで、オレンジもしくは青みがかかってしまいます。