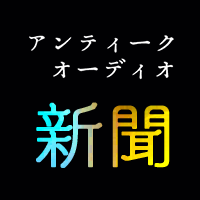粒立ちが良いとは、アンサンブルにおいて個々の楽器の音が重ならずに個別にしっかり聴き分けられるという意味で使っていると推測する。
この表現は、私にもイメージが掴みやすくて言いたい事が解る気がします。
スピーカーのユニットや、アンプの性能が悪いと本当にアンサンブルで楽器の音が重なり合ってうるさく感じる音があります。
その点、個々の楽器がそれぞれしっかりと聴こえる音は大きな音でもうるさく感じません。
粒立ちとは、ご飯を炊いた時に一粒一粒がぷっくらしてべったりしていない様に例えているのだろうと思いますが、この表現だけは良い表現だと感心します。
※音というのは人間の耳の構造上、極めて曖昧な存在です。
その音を言葉で表現するのは更に難しいのですが、評論家諸氏の独特な言い回しが更にこれを難しいものとしている気がしてなりません。
また、正確な意味も知らずに他の評論家の表現を真似ている若い評論家もいるので、オーディオ評論家の評価を鵜呑みにするのは大変危険です。
オーディオは製品の性質もさることながら、鳴らす環境やソースによって大きく鳴り方が変わるし、感じ方はその人の趣向が強く反映されます。
評論家の多くが「~感」という言葉を使います、つまり自身の感覚であって、そこに根拠も示すべきエビデンスもありません。
オーディオ製品は、他者の評価は参考程度に聞いておいて自分の耳で確認し、自分の好きな音を探すのが一番でしょう!

腰が強い/押しのあるとは、中音域が充実しており、締まった低音域の音を指して言うのだと推測する。
私も、こういった音を骨太な音と表現しているが、低中音域が締まっていると力強い音に感じる事は確かです。
こういった音はマニアの間ではカマボコ型と表しており、ジャズやロックファンには堪らない音なのです。
ベースやバスドラがはっきりと分かれて聴き取れ、そこにサックスやトランペット、ピアノやボーカルが軽快に乗り、更にはハイハットやクラッシャーの音がしっかりと前に出てくるように聴こえてくるのです。
本当に他に表現が思い付かないほど、その表現の感覚は理解できます。
私は、こんなジャズのライブハウスで聴くような音を求めてスピーカーやアンプを日夜変えまくっているのです。
※音というのは人間の耳の構造上、極めて曖昧な存在です。
その音を言葉で表現するのは更に難しいのですが、評論家諸氏の独特な言い回しが更にこれを難しいものとしている気がしてなりません。
また、正確な意味も知らずに他の評論家の表現を真似ている若い評論家もいるので、オーディオ評論家の評価を鵜呑みにするのは大変危険です。
オーディオは製品の性質もさることながら、鳴らす環境やソースによって大きく鳴り方が変わるし、感じ方はその人の趣向が強く反映されます。
評論家の多くが「~感」という言葉を使います、つまり自身の感覚であって、そこに根拠も示すべきエビデンスもありません。
オーディオ製品は、他者の評価は参考程度に聞いておいて自分の耳で確認し、自分の好きな音を探すのが一番でしょう!

臨場感とは、例えばコンサートホールやライブハウスに居るかのような気分になる音ということを言っているのだと推測する。
もしそれが本当なら、そう評価されたオーディオ機器は飛ぶように売れるはずであるが現実はそうではない。
本当の意味での臨場感を味わうのであれば、最低でも20坪(40畳)ほどの適度な響きの有る部屋で、ホーン型スコーカーとホーン型ツイーターの付いた大型スピーカーを100W以上のパワーで駆動できる高級アンプで大音量で鳴らすことです。
これは私見ですが、写真で見ると10畳ほどの吸音されたモニタールームでエントリークラスやミドルレンジのアンプやスピーカーを評価し、「臨場感溢れる」という表現が何故できるのかは大いに疑問である。
その評論家は、いったいどんなライブに行っているのでしょうか?
表現方法は個人の自由ですが、人によって感じ方があまりにも違う言葉を使うのはあまりにも感心しない。
※音というのは人間の耳の構造上、極めて曖昧な存在です。
その音を言葉で表現するのは更に難しいのですが、評論家諸氏の独特な言い回しが更にこれを難しいものとしている気がしてなりません。
また、正確な意味も知らずに他の評論家の表現を真似ている若い評論家もいるので、オーディオ評論家の評価を鵜呑みにするのは大変危険です。
オーディオは製品の性質もさることながら、鳴らす環境やソースによって大きく鳴り方が変わるし、感じ方はその人の趣向が強く反映されます。
評論家の多くが「~感」という言葉を使います、つまり自身の感覚であって、そこに根拠も示すべきエビデンスもありません。
オーディオ製品は、他者の評価は参考程度に聞いておいて自分の耳で確認し、自分の好きな音を探すのが一番でしょう!

なんちゃらサウンドとは、良い表現が見つからない時の言い逃れ的な表現で、具体的に何かを指しているのではないと推測する。
例えば、JBLのスピーカーの音を「カルフォルニアサウンド」とか、DALIのスピーカーでは「ヨーロッパの森林浴サウンド」などと表現する事があります。
また、昔のそのメーカーの古き良き時代の音を指して「オールドヤマハサウンド」などとも言います。(これだけは致し方ない表現だと思います)
多くの人は、これを読んでどんな音かを想像できるでしょうか?
そもそもですが、オーディオメーカーの多くは本社のあるその地では製造しておらず工場の多くはアジア圏に在ります。
いったいこれを、どう説明したらいいのでしょうか?
プロなら、しっかりとしたエビデンスに基づく根拠を示さないと駄目だと思うのです。
※音というのは人間の耳の構造上、極めて曖昧な存在です。
その音を言葉で表現するのは更に難しいのですが、評論家諸氏の独特な言い回しが更にこれを難しいものとしている気がしてなりません。
また、正確な意味も知らずに他の評論家の表現を真似ている若い評論家もいるので、オーディオ評論家の評価を鵜呑みにするのは大変危険です。
オーディオは製品の性質もさることながら、鳴らす環境やソースによって大きく鳴り方が変わるし、感じ方はその人の趣向が強く反映されます。
評論家の多くが「~感」という言葉を使います、つまり自身の感覚であって、そこに根拠も示すべきエビデンスもありません。
オーディオ製品は、他者の評価は参考程度に聞いておいて自分の耳で確認し、自分の好きな音を探すのが一番でしょう!

温もりを感じる/人間味のあるとは、刺激が少ない音を指していると推測する。
つまり、聞きやすい音だということを表現しているのかと思いますが、ある意味では「適度に抑えられた音」とも取ることができます。
確かに、刺激が少なく聞きやすい音は長時間聞いていても疲れません、これは良く解ります。
ただ、読む人によっては最悪な評価と受け取られ可能性の高い言葉です。
これは聞く音楽のジャンルによって異なりますが、迫力や刺激的な音を求めるジャズやロックファンが「温もしを感じる音」という評価のものはまず買わないでしょう。
サックスやギターなどを生で聴けばすぐ解りますが目の覚めるような極めて刺激的な音です、これをどこまで再現させることができるのかとジャズやロックファンは日々苦労しているのです。
イージーリスニングやクラシックなどを作業用BGMとして小さな音で流すような場合には好まれる表現だと思いますが、それならエントリークラスのミニコンポで充分であり敢えてハイファイオーディオ製品を購入する必要もない。
尚、「シャイな」、「謙虚な」と言う表現もほぼ同義語だと推測する。
※音というのは人間の耳の構造上、極めて曖昧な存在です。
その音を言葉で表現するのは更に難しいのですが、評論家諸氏の独特な言い回しが更にこれを難しいものとしている気がしてなりません。
また、正確な意味も知らずに他の評論家の表現を真似ている若い評論家もいるので、オーディオ評論家の評価を鵜呑みにするのは大変危険です。
オーディオは製品の性質もさることながら、鳴らす環境やソースによって大きく鳴り方が変わるし、感じ方はその人の趣向が強く反映されます。
評論家の多くが「~感」という言葉を使います、つまり自身の感覚であって、そこに根拠も示すべきエビデンスもありません。
オーディオ製品は、他者の評価は参考程度に聞いておいて自分の耳で確認し、自分の好きな音を探すのが一番でしょう!