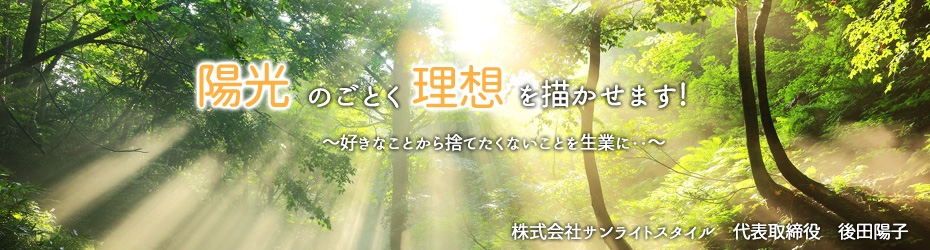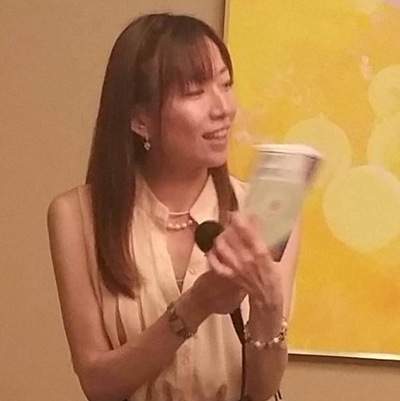2025年2月19日 11:00
薬酒を作りをはじめて10年になりますが、熟成期間が長くなるほど、どの薬酒も最終的にものすごく甘くなります。
特にタンポポ根酒の甘さには驚きます。
あれほどの強烈な苦さが緩和し、信じられないほどまろやかに飲みやすく変化していました。
自身の体質にあった薬酒を見つけて、毎日継続してごく微量を飲用することで病気になりにくい体を作り上げることができるといわれています。
近年、お酒は「百薬の長」ではなく「百害あって一利なし」と言われていますが、
余計な添加物などを使わず醸造・発酵・浸漬などを通してハーブの成分をお酒に移行させた薬酒には、生薬の薬効があります。
薬酒というと、なんとなく身体に良い成分(薬効成分)を取り入れる、といったイメージがないでしょうか。
もちろん間違いではありません。
しかし、100%正しいというわけでもありません。
そもそも漠然というこちらの「薬効成分」とは何なのか、これらがどう作用するのか、明確に説明できる方は少ないのではないでしょうか。
イメージだけで薬酒摂取してしまうと、健康への効果が期待できないどころか、身体に悪影響にもなりかねないと言われています。
植物は天敵である動物から身を守るための毒をもっています。それがアルカロイドです。
アルカロイドにはカフェイン・ニコチン・コカインなどさまざまなものがあり、植物によってさまざまです。
植物に触って皮膚がかゆくなったり、草を食べて舌が痺れたりするのも、アルカロイド。
このアルカロイドが薬効成分と言われるものです。
このように、重要なのはアルカロイドは本来人間にとって毒であること、つまり「薬効成分」とは毒性にも薬効にもなる、陰陽一体の薬理作用をもたらす成分であることです。
もちろんアルカロイドの毒素はアルコールによって分解されているのですが、ただ、ごく微量の毒素まですべて分解しきれているといいきれないものが薬酒です。
薬酒が身体に良いとされてきたメカニズムは、単純に良い成分だけを摂り入れているのではなく、同時に「極めて微量の毒」も体内に摂り入れることにもあったのです。
しかし、なぜ毒を飲むことが健康につながるのでしょう。
それは、毒を毎日微量ずつ、継続的に、摂取することで、毒に負けない「強化した肝臓を作ること」にあります。
虚弱な肝臓を持つ身体は解毒の機能が弱く、毒やウィルスに対する抵抗力がなく病気にもかかりやすくなります。
昔から言われる「毒をもって毒を制する」という先人の言葉にあるように、
微量な毒の継続的摂取によって毒に負けない内臓へと鍛えること、ここにも薬酒の健康への効能があると言われています。
そして植物を漬けるアルコールにも同じことが言えます。
植物の毒素を無害化するだけなら、お酢や塩でも可能です。しかし薬酒はなぜアルコールで漬けるのでしょうか。
冒頭に書きました通りアルコールが「百害あって一利なし」と言われてしまう理由は、アルコールは身体にとって本来は毒でもあるからです。
お酒を飲み続けているとアルコールに強くなるのも、毎日微量のアルコール(毒)の継続的摂取で肝臓の解毒機能が強化されているためです。
薬酒を「体に良い成分だから」とたくさん飲んだり、元気を出したいときだけたまに、といって飲まれる方もいます。
しかし、一気に飲むのは薬効成分が強すぎて身体に悪影響を及ぼす可能性があります。
薬効成分とアルコールのダブルパンチで肝臓に負担がかかり逆に肝臓を悪くしてしまいます。
そしてたまに飲んでもあまり肝臓強化にはつながらず、これも中途半端に肝臓に負担がかかる原因にもなりえます。
大切なのは、本当にわずかに微量ずつ、なるべく継続的に、続けること。
薬酒作りは、時間こそかかりますがリカーに漬けることで成分を抽出する、というとても簡単な仕組みです。
身体機能の個性はさまざまです。ぜひ自身の体質にあった薬酒をみつけて、無理せず微量ずつ、継続して飲用したいですね。
***