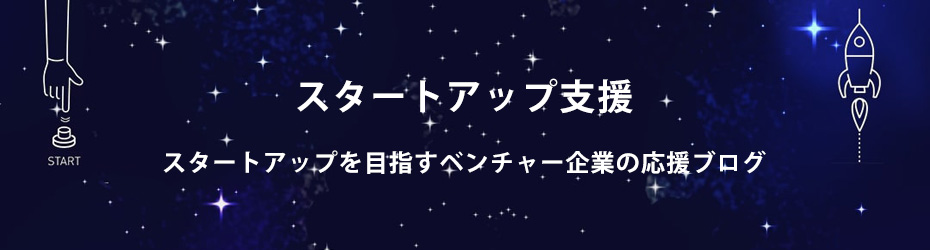自然をよく観察すると実に大きな学びがあります、その一つにいかなる事項も必ず遅延という事象が存在している事実が理解できます、一日を考えると太陽が最も高い所に昇る昼時よりも少し過ぎた午後になり気温が最高潮に達します、年間を考えると昼が最も長い立夏過ぎて暑さを増してきます、同じように夜が最も長くなる立冬過ぎて寒さが増してきます。
人間の体調も夏の疲れは涼しくなってきた秋に現れます、同じように冬の寒さを凌いだ疲れが温かくなる春以降に現れます、ビジネスも人が行うものであるなら必ずそこには遅延が発生すると考えるのが自然の摂理どおりではないかと思うのです。
事実全社一丸となっての事業推進では行動の結果は行動のピークを過ぎた後に現れてきます、したがって行動しているときには結果をじっと待つ余裕が重要となってくるのです、資金繰りなどの計画は行動と結果との遅延を意識して最初から織り込んでおかないと結果が出るのを待つことができずにガス欠で動けなくなります。
事業推進だけではありません、販売実績も実は忘れたころに徐々に結果が現れることなど珍しいことではありません、動けば直ぐにも結果が現れると考えるのは早計で何事も結果が出るのを楽しみに待つくらいの余裕が重要です。
どんなことも「行動した結果は遅延して現れる」、これを先に念頭に入れて計画に織り込んでおくことです、そうすれば結果が出ないと慌てることも焦ることもなくなるでしょう、常に心にゆとりを持ってビジネスしたければ、何事も最初から結果は遅れて現れることを意識してほしいと思います、「果報は寝て待て」の本質はこういうことです。
ただ何もしないで待っていても当然結果は何も起こることはないのは言うまでもありません、先ずは「待つ期間を考慮して資金調達する」、そして「やるべき事を手抜きせずプロセスを踏んでしっかり行う」、最後に「寝て待つ」、これが極めてシンプルな成功の方程式です、そしてこれを別事業で複数同時に並行して行う、こうすればどこかの事業で常に結果が継続的に表れていることになるのです。
「時は金なり」という諺があります、そして多くの人がビジネスなどでよく使っています、例えば「ビジネスに直結する事を優先して今必要でない事は後回しにする」、「無駄な時間を過ごすな」などの言動とセットで使われ、相手を納得させることでは便利な諺でもあります。
私的にはこの諺がズバリと当てはまるのではないかと思うのが通勤や移動時間です、これは絶対的な時間を奪われてしまうので特に優先して考えるようにしています。
経営者であれば自宅とオフィスは近いほどメリットは大きいです、特にビジネスチャンスを逃さないという点においては最優先する必須事項です。
突発的事項に対応できる為には30分以内にオフィスに到着できるところに自宅を構えるのは定石であり私は過去30年以上最優先しています、休日の突然の訪問依頼や急ぎの書類の受け渡しなどクライアントの都合に合わせた対応が瞬時に取ることができるからです。
またミーティングなどでの訪問による移動時間、これもほぼ都内であれば30分前後で到着できるようなところにオフィスや自宅を構えることが時間を有効に使えます。
更には訪問する予定の段取りでは私は訪問する予定はできるだけ同じ日に纏めるようにしています、そして打ち合わせは端的に短時間で終わらせるようにします、これなら1日で数ヶ所をぐるっと回れ短時間で多くの案件をこなすことができます、そして同様に来客の予定も同じ日に纏めて詰め込みます。
こうすることで1日で来客と訪問を組み合わせた場合に比べて2~3倍多くの案件を消化することが可能になります、経営者の時間はお金と同じです、無駄に時間を割いているから利益率はどんどん下がりキャッシュフロー問題で常に頭を悩ますのです。
ビジネスが上手くいっていない人の多くは打ち合わせがダラダラと長く移動時間ばかりに時間を取られては無駄に大切な時間を費やしています、1日は誰にとっても同じ24時間です、これをどれほど有益に使えるかどうかが成功する人としない人の大きな差となるのです。
同じことを互いに話しているはずなのに「何故これほど話が噛みあわないのだろうか」、と思うことがありませんか、この同じことを話しているのに噛み合わない原因ですが多くは「コンテクスト」の不一致によるものだと推測されます。
つい先日もこんなことがありました、私は独自の情報サイトの有用性を話しているのに相手はそれに対して自身が付けたい具体的なドメイン名を上げてきます。
そして私は「今話しているのはそういう細かなことではなくて根幹は理解していますか?」と少し強めの口調に変わってしまいました、同じサイトについて話をしているのに私は根幹の有用性について相手は細かな枝葉の部分についてでは話が食い違うのは当たり前になってしまいます。
この「コンテクスト」という概念は言語学においての「知覚」を定義する用語で「話をする場合に背景・状況・関係性などを共通化する必要がある」と説いているものです、例えばワインの話をしているとしましょう、片方が白ワインでもう片方が赤ワインの話であれば同じワインでも飲み方や合うつまみの話も違ってきますから当然のこと対象が異なることに気がつくまでは話がすれ違ってきてしまいます。
ビジネス会話ではこの「コンテクスト」という概念を頭に入れて言葉は同じだが相手と背景・状況・関係性などを共有しているか、つまり対象を限定共有化させて話をするということが重要になります。
更には文章では曖昧な表現は多くの誤解を与えることになります、テクニックとして曖昧さを表現する以外はできるだけ対象を限定共有化させるということが重要だということを念頭に置いていただければと思います。
起業家の多くは前向きな人だと思います、未来に希望を持って自身で事を成そうとしているのですから当たり前だと思います、ただその前向きさが力の入れどころを間違えて前のめりになっている人も時々見かけます。
起業家にありがちな勘違いは「このビジネスは必ず上手くいく!」と思い込んで行動してしまうことです、そしてその陰に潜むリスクや社会的な責任を見落とすようになってしまいます。
どんなビジネスにも斬新なアイデアや過去の栄誉は必要ありません、斬新な技術や新しい思想を埋め込んだビジネスは世に溢れていますが上手くいくかは別の話です。
ビジネスは顧客や支持する人達への誠意やビジネスセンス、加えて経営テクニックやパートナーを含めた信頼・信用が最も重要です、最終的には企業として当たり前なサービスを如何に安定的に継続させられるかがすべてです。
「上手くいく!」と思って始めたのに「こんなはずではなかった」と心が折れてしまうようでは経営者失格です、そんな予定外のことなどは「想定の範囲」と流せないようでは先が思いやられます。
起業当初はトラブルの連続は当たり前で経営者として成長していく為の試練です、その過程においてビジネスセンスや経営テクニックが磨かれていくのです。
「上手くいく!」と考えるとちょっとした躓きも感情に流されてしまいます、起業家にとって重要な姿勢は「上手くいく!」と思い込みによる前向きさではなく「絶対上手くやってやる!」という信念で上手くやる為のテクニックをしっかりと身につけることです。
経済シンクタンクがよく話題にする「企業において大きな出来事はリズミカルに訪れる」ということの根拠を探る目的で自身のビジネス年表を作成したことがあります、その結果驚いたことに私のビジネスサイクルは約12年単位であり「子年」に大きな変化が起き「寅年」に拡大成長していました。
会社設立が1984年の「子年」でフリーSEでの全盛期に即戦力5名と共に何人もの中途採用や新卒社員を雇い入れての船出でした、順調に滑り出したのですが1年後に分社し設立当初の即戦力メンバーは全員いなくなってしまいました。
そこからが面白いのです、経験の浅い社員十数名を徹底的に教育し見事1年で収益を回復させ急成長を遂げました、これが1986年の「寅年」です、大規模受注も決まり世はバブル経済の真っただ中で当社は設立来最高益をここから6年連続で達成するのです。
次の「子年」の時には大規模オフィスビルに引っ越し、そして「寅年」ではまさにこの世の春を謳歌し特許収益も加わり売り上げがピークに達しました、そして念願の自社ブランドで日本初の小型ネットワークカメラや高圧縮動画録画機などのプロダクツ事業を開始しました。
その後は待望の新事業でのビジネスモデル特許を取得し上場企業の傘下に入ったとはいえ特許事業で市場を独占し事業規模数百億円のビジネスを作り上げたのが2008年の「子年」でした、このように設立からの年表を作成してみると面白いように「子年」から次のステージが始まって「寅年」から数年間拡大成長していることが解ったのです。
どの人にも企業にも必ず一定のリズムが存在しています、まずは自身のリズムを探ってみるのも意味があると思います、そして先の「子年」の2020年には新事業で大手企業との契約や自社商品の展開など新たなる局面が開かれ「寅年」の年末に大規模増資を行いました、いったいこれからの数年間はどんな世界が広がっていくのでしょうか?