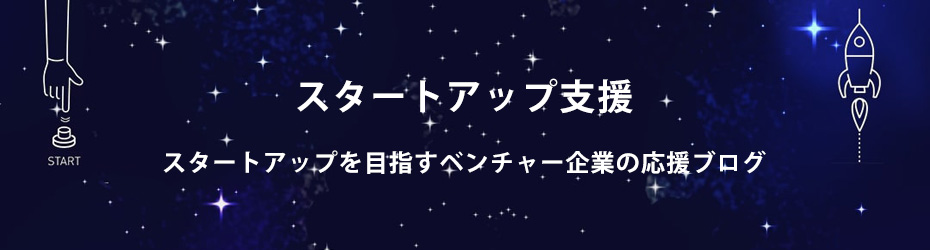私が考案し一時期サービスとして事業化していたたブランディング手法である「オンリーワンブランディング」とは、その人独自の事業を確立しブルーオーシャンを悠々と泳いでいただくことを最大の目的としたサービスでした。
事業というのは一時的なお金を得るための存在ではありません、未来永劫お金を生み続けることが肝要なのです、世に存在している自称ブランディングプロデューサーなどが展開する一瞬の「良い思い」を創造することを目的とした手法をブランディングとは呼びません。
ここで「ブランディング」とは「CI(Corporate Identity)」の一つの手法で「顧客の信頼を得て企業価値を高める企業戦略」を指し、決して安易にブランドを作り上げて知名度を上げることではありません、ちなみに「CI」とは「統一されたイメージやデザインによって企業文化を構築し価値を高めることによって顧客と利益を共有する」というのが最終目的です。
巷にはこのどちらでもない「ファンを増やし有名になって集客に活かす」というSNSを使って知名度を上げるのが目的の似非ブランディングが横行しています、これらはブランディングでもCIでもマーケティングでも何でもなく仮想空間上でカリスマを作り上げては自己満足させてあげるのが関の山です。
ブランディングに必須である「継続してお金を生み続ける手法」を指導するわけでもなくビジネスには無関係の結果しか残りません、経営とは未来永劫継続するものです、つまり瞬間の名声ではなく継続した事業を通して信頼と実績を勝ち得ていかなければなりません。
商品やサービスの信頼は一過性のものではなく進化しながら顧客満足度を維持していかなければならず、これが企業の第一義である「企業価値向上&顧客満足度」に繋がるのです。
企業価値とは代表者が有名になることではありません、継続した信頼感から自然に口コミなどによって商品やサービスの知名度が上がるようにするのが本物のブランディングであり経営者が真剣に考えるべき事項なのです。
自身が有名になりたいのであれば法人を作る意味も持つ意味もありません、個人事業主やフリーターの方が法的な柵もなく余程上手くいきます、経営者であるなら事業と企業の価値と信用力を向上させ継続させることに時間と労力をかけていただきたいと願うばかりです。
今の職業はあなたに向いていると思いますか、それしかできないと思いこんでいて他にできることを考えないようにしていませんか?
実はいろいろな経営者や起業したい人と接してきてあることに気付きます、それは自身ができる事と向いている事とを違う次元で考えているということです、「これをやろう!」と思って起業しやり続けてきた結果において充分な利益が出て経済的に自立できているでしょうか?
「石の上にも3年」と言います、これは最低でも3年続けてみないと上手くいくのか否かは解らないということです、逆を言えば3年以上同じ事を続けてきて充分に利益が出ていないのであれば今後も上手くいく可能性は極めて低いと言えます。
好きな事とできる事、更には向いている事とはイコールではありません、まずはやり出した事業を最低でも3年は続けてみることです、それで黒字転換できないようであれば今度は潔く事業変革すべきです。
変革できない人の多くは「それしかできない」と勝手に思いこんでいます、でも私から見ればもっと別の才能を観て取れます、才能や能力は自身の武器、でもそれでお金を得ることは別次元のテクニックが必要なのです。
こればかりは腕を幾ら磨いても経験を幾ら積んでも身につくものではありません、逆に言えば技術も経験も無くても成功できる人は事実沢山います、やりたいことで成功するには腕を磨くよりも稼ぐテクニックを学ぶことのほうが如何に重要であるかということです。
絵の上手い人は沢山います、でもその人たちの絵は売れていますか、ビジネスは技術や能力ではないのです、経営者が学ぶべきものは違う次元にあるということを理解すべきです。
技術も経験も人脈も無くても幾らでも稼げます、それを持っている人と強い信頼関係を築くだけで全ての事が一瞬で進みます、もっともそういう人と信頼関係を得るのが物を作る以上に難しいのですがクリアさえすればやりたい事で事業化し利益を出せるのです。
「稼ぐテクニック」というのは実は経営そのものだということです、全てを備わっている人と組めるかどうかも重要な経営です、起業したのなら経営者として経営をしっかり行ってほしいと思います。
近年の日本政府による政策の一つに就労人口を増加させ税収の確保が上げられます、具体的な施策として若者・女性・高齢者の起業奨励に力を入れています。
その背景もあり一時期は起業ブームが起こりましたが、ブームに乗って起業するも収益事業を構築できずに早々に破たんする人も増えています、これもまた現実です。
近年では起業1年以内の実質的な破綻率は実に80%という数字も出てきているのです、これらを考えるに「経済的余裕のあるうちに起業したほうがよい」ということが言えます。
起業してビジネスが軌道に乗るまでには最低でも数年間はかかります、これは誰がやっても同じです。
個人事業である程度のビジネスが確立されてからの起業の場合を除き事業計画の策定に始まりホームページの構築に顧客の確保と、あっという間に利益がでるどころか出費し続けるだけで2~3年は経過してしまいます。
そして、期待の融資は実績が無いとなかなか厳しいのも事実で取引状況や収益などはかなり信憑性のある情報を開示しなければなりません、したがって資金調達も容易ではありません。
つまりギリギリの状況で切羽詰まっての起業では、事業構築する前に経済破綻を起こしてしまうのは当たり前なのです。
今は副業を許可する会社も多くなりました、給与を貰っている間に起業して充分に準備してから退社して本格稼働する、これが経済的な観点で言えば理想的な現代の起業スタイルなのかもしれません。
ただ覚悟を決めて「どんな状況になろうが克服して絶対に成功させる」という強い意志が有る場合は潔く退社して裸一貫から起業する、これは上手くいけば極めて短期間で成功を収める場合が多いのも事実です。
「晴天の霹靂(へきれき)」とは予想外の事が突如起こるという意味の言葉です、自分が正しいと疑いもなく信じていた事がある日を境に結果的に人を騙し多くの人を傷つけてしまったという事件を時々耳にします。
例えばある会社に魅力を感じて就職をします、その会社の社長は非常に人間味もありいろいろなことを知っています、その会社のやっていることは最先端のサービス業であり、それによって人が喜んでくれるというまさに自分の理想郷だと思っていた・・・、そして今まで以上にその会社で頑張り辛いときも正義感に燃え社長と共に夢を語り合ってきた・・・。
ところが会社で行っていたインターネットを活用した商法が突然違法(出資法違反)であると摘発され、顧客からはクレームの嵐で今まで正義感があると信じて疑いも無かった社長が社員を置いて早々と夜逃げ、そして会社の残余資産は差し押さえられ家族と共に路頭に迷う・・・、更に今まで仲の良かった顧客からは「詐欺」呼ばわれされ弁護士会が発足し賠償請求が社員等に浴びせかけられた・・・、これは過去私の知人に実際に起きた事実です。
私は常日頃その知人には「会社のやってることも社長の考えも何かおかしいんじゃないのか?」と言ってきたのです、でも彼は聴く耳を一切持ちませんでした、逆に私が悪者扱いされまずい酒の席になったことも何度もありました。
人を信じることは悪いことではありません、むしろ好ましいことです、ただし人を見る目を持ち真実を見抜くことが出来なければ例え自分が正義に燃えていたとしてもこういうケースに巻き込まれる可能性が充分にあるということを理解するべきです。
食品偽装で摘発された会社などの社員もきっと同じことではないでしょうか、また違法ではありませんが結果的に事業が破綻し多くの被害者を出したリーマン・ブラザースの社員なども同様といえます。
人は意味の無い時間もお金も使ってはくれないのです、もしそういうことがあるのなら何かを真剣に伝えたいということです。
その知人はその後極度の人間不信に陥り行方知れずになってしまいました、時代が変わり価値観が変われば白が黒に変わるのです、あなたの正義が最悪の犯罪に変わらないとは誰にも断言できません。
時代の変化とはそういうものなのです、何事も冷静に真実を見極める能力を身につけることが肝要です、そもそも真実を追求しようとしない人に「正義」を語ってほしくはないと思います。
「何度も言っておいたので伝わっているはずだ」と言う人がいます、ところがいざ蓋を開けてみるとその期待していたはずの人が予想だにしない期待はずれな行動をすることがあります。
上司の「言って聞かせる」はだいたいが部下には通じていません、部下からすれば「上司が何か言っていたな」ぐらいの気持ちでしかないのでしょう、したがって上司が「期待したとおりの働き」は全くといっていいほどできるはずもないのです。
賢い上司とは、「部下が自ら状況を理解し動くように促す」ことを念頭に教育する人です、自ら状況を理解させるためには「今、何を優先すべきか」を教えていかなくてはなりません、それは口頭で教えるのではなく身体に染み込ませなくてはなりません、つまり失敗も含めた経験を通して理解してもらう必要があるのです。
そして口頭で教えるときには状況を具体的に想像できるよう例えや過去の実例を通して幾つかのシミュレーションを提示することが重要です、セブン・アンド・アイホールディングスの鈴木会長は いくら叱り飛ばしてもお店の清掃をしない店長に状況を理解してもらうため薄暗くて汚い店舗に無言で連れて行ったそうです、そこで「お前はこの店を見て買いたいと思うか?」と一言聞いたそうです。
人が自ら動くようになるためには 「具体的に見えるもの、自分で理解できるもの」を目の前に示して 自らが判断できるような状況を作ってやることが肝要なのです、これが生きた教育というものです。
ただし何をしても情けをかけても通じない人は何処にでもいます、厳しいようですが教育する時間と労力が無駄というものです、自ら離れて行くように誘導してあげるのも愛情だと思います、それが双方にとってベストな方法なのです。