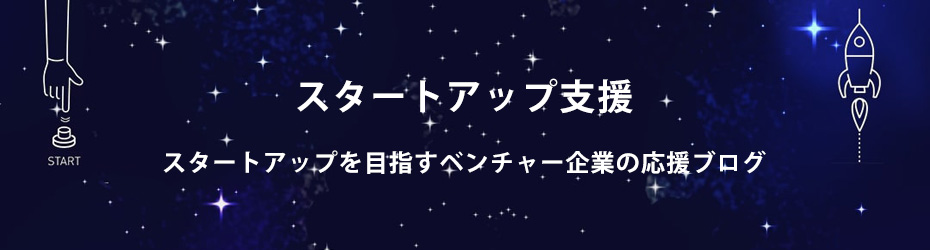「パラサイト」とは「寄生」の意味であまり聞こえは良くないのですが、これからお話しすることを読んだあなたは確実にカルチャーショックを受け意識に大変化をもたらすことになるでしょう、私の知りえる限り最強にして究極の「パラサイト」はミトコンドリアです。
ミトコンドリアはなんと植物や動物など真核生物の細胞の中に寄生する生命体でRNAという遺伝子情報をしっかりと持っています、RNAはDNAと同じ遺伝子情報を保管する媒体でDNAは2本のリボン状ですがRNAは1本のリボン状であり未熟な遺伝子媒体で古菌類は全てこのRNAを持っています。
このミトコンドリアはいつの時代か進化の過程で真核生物の細胞の中に寄生しました、つまり細胞分裂のたびに自身の種の保存ができるわけです、そして最近になり時間管理や各種生体メカニズムに深く関与していることも解ってきました。
オーバーな話しですがミトコンドリアは自身の種の保存を行うために寄生している本体を都合の良いようにコントロールしているという仮説が浮上しています、私も各種の情報を集めて研究していますがこの仮説は極めて正確な事実ではないかと考えています。
その意味でいうところの「パラサイトビジネス」ですが、これがものの見事に上手くいくと自らは何もせずして利益を得る究極のビジネスに成り得ます、例えば代理店ですがメーカーが儲かるように仕組みを作り上げることでメーカーは各種の保護政策を打ち出してくれます。
メーカーも商品が売れれば儲かります、商品を売ってくれる代理店を丁重に扱うのは当たり前です、活動資金は勿論のこと場合によっては新事業の資金まで出資してくれる場合もあります、現在活躍している大手ベンチャー企業はほとんどが起業当初はこの「パラサイトビジネス」を実践し成長を遂げてきました。
「パラサイトビジネス」の成功は本体を喜ばせることに尽きます、本体が幸福であれば自身も安泰なのです、そして仕組みや流れが確立できた後は自身が何もせずともお金が回るようになります、これが「既得権」という無形財産なのです、手っ取り早く勝者になりたいのであれば「パラサイトビジネス」手法を取り入れてみては如何でしょうか。
自己実現を目指して独立起業し期待に満ちてワクワクしながら張り切っていたのでしょう、しかしそのワクワク感は起業後数ヵ月で一瞬にして思うように進まないことでのイライラ感に変わってきます、そして次に襲ってくるのが生活の不安であり更には見えない将来ビジョンに対する失望感との戦いです。
でもこれは極めて正常な独立起業の人の状況と心境です、ソフトバンクも創業3年間は収益がほとんど上がらずどん底からのスタートだったのです、松下幸之助もスタート直後から辛酸を舐めながらの三畳一間の家内興業でした、何年間も明日が見えない状況下で苦しんだのです、起業当初に過去の実績で順調にいく人も稀に見られます、しかし結局は同じことです、半年もしないうちに思うように進まない状況と資金繰りの二重のジレンマに陥ります。
ここまでは勝者も敗者も同じ状況になりますが起業3年経った辺りから両者の状況は大きく乖離してきます、勝者となれる人は大きな気付きをもって自身を積極的且つストイックに進化させていきます、その前向きな姿勢に周囲も動かされ協力的になります、そして状況は少しずつ好転しはじめてくるのです、その後は経営や事業成長に必要な人の信頼と協力を得て自身も企業も一気に成長していきます。
対して敗者となってしまう人は3年辺りで「自己実現など夢のまた夢だった」と諦めてしまいます、そして行きつく先は落ち込んだ心を癒してくれる家族や人のところです、この時点で姿勢は既に守りに入っています、そして有益な人からも距離を置かれるようになります、人生とは守りに入った瞬間に転がり落ちていきます、そして数ヶ月で人が変わったようになっていきます。
自身を脅かす事項と戦わなかったらどうなるでしょうか、そうです戦わなければあっという間に自身が最も嫌だった状況に脳が占領されてしまうのです、後は必死で与えてくれる人にしがみつくしか守る方法がなくなってきます。
勝者と敗者の違いはたった一つです、どん底から這い上がる前向きな強い気力を持ち続けるか、その重圧に押しつぶされて明るい未来を諦め現状生活を継続させることに甘んじるか、すべてが自身の精神力の強さ次第なのです。
ここでいう精神力とは守りの精神力ではなく攻めの精神力です、意外や守りの精神力が強い人は攻めの精神力が極めて弱いのです、だから更に苦境下でできることは現状の生活を必死で守るという頑なな思考になってしまうのです、這い上がれる人は次々と襲ってくる重圧や障害をクリアして更に成長していきます、守りに入った人は未来を創造する為のお金さえも惜しみ人間性もどんどん小さくなります。
谷深ければ山高し、底が深くなった人ほど這い上がるには大きなエネルギーを必要とします、最終的に行きつく谷底である「人生破綻」の前に最後の気力を振り絞って少しでも浅いうちに這い上がっていただきたいと思います、「経営破綻」などは一つの勲章です、「人生破綻」したら生きながらも人生は終わっています。
コンビニエンスストアの新業態を模索していたローソンは「ローソンマート」の新規サービスを開始し「低価格路線」と「価格弾力性」でセブンイレブンに対抗するための秘策を打ち出したことがあります、ところが3年間で500店出店という大規模プロジェクトは1年もしないうちにプロジェクト自体が崩壊してしまったのです。
ローソンストア100に限界を感じた首脳陣がもっと価格に弾力性を付けたいとのことから100円の枠を取り払い、お客さまにより適正な価格で商品を届けたいという思いで「ローソンマート」は産まれたのですが狙いは大きく外れてしまいました。
私は発表当初から「これはうまくいかないだろうな」という予感がありましたが敗因はどこにあるのでしょうか、一番大きな問題点は「自分が何者であるか」をはき違えてしまったことではないでしょうか、コンビニエンスストアとスーパーは全く存在コンセプトが異なります、「価格の弾力性に限界を感じた」時点でここに気付くべきことだったと思うのです。
コンビニエンスストアとスーパーのビジネスモデルの違いは明白で、スーパーは大量買い付けによる低価格路線を顧客に打ち出す一方で店内の品数を増やし「ついで買い」を誘い顧客の販売単価をいかに上げるかを基本とするビジネスモデルです。
対してコンビニエンスストアは生活に必要最低限のものが「何時でも必ずここにある」という信頼感を前提にした定価販売による高付加価値高利益追求型のビジネスモデルなのです、両者はその仕入れルートも物流も利益の追求の仕方も異なり「存在価値」が全く違うのです。
コンビニエンスストアという業態の本分をはき違えてしまっては一時的に良くともいずれ大きな失敗をもたらすことになるよい例ではないでしょうか、他者と競合するなら自分の本分は何かを忘れるべきではありません、経営者が自分らしさを失ったとき何の意味も価値も生まない面白味の無い企業に成り下がってしまうのです。
マイケル・E・ポーターの著書に「競争の戦略」・「競争優位の戦略」という有名な書籍があり自分たちの事業にとって何が敵対しており、それらに対してどのように対策を取るのか、更には事業の業績をどのようにあげ維持していくかについて詳細に書かれている名著です、ファイブフォースやバリューチェーンといった言葉を聞いたことがある人は多いと思いますがポーター博士はこれらフレームワークの生みの親です。
さて事業家にとって事業の持続的な成長は永遠の課題です、 しかし時代の移り変わりが激しい現在では1つの製品やサービスが長年継続し収益を生み出し続けることは稀なことです、次々と新しいサービスや事業を生み出し続けない限りは数年で力尽き事業から継続安定的に収益をもたらし続けることは難しいばかりか会社の足元までが揺らいでしまいかねません。
大企業ですらそうなのです、ベンチャー起業なら一瞬の判断ミスが会社の命運を決めかねないのです、では素早く移り変わる世の中についていき自分の事業を軌道に乗せるためにはどうしたら良いのでしょうか。
その答えは「売り逃げ」することです、ある事業が高収益をもたらすと分かった瞬間に資本を集中投下し収益を最大限まで引き上げピークを迎えるころに撤退の準備をしタイミングを見計らって早い段階で撤退することです。
人は売上や業績が上がっている時にはそこから衰退することを考えません、悪いことに過去の栄光を忘れられずに過剰に追加投資する場合もあります、バンダイが「たまごっち」で売上ピークと資本投下の時期を見誤ったように、シャープが液晶に過剰投資してしまったように、未来ビジョンを見誤ると一気に衰退の道を転げ落ちることになります。
既にその事業の収益がピークに達していると感じたのなら収益が最大のうちにあるだけのリソースを投下して回収を早め、現状の収益にしがみつかずにさっさと撤退の方法とタイミングを考えるべきです、そして回収した資本の投下先は新たな事業のために使い芽吹きを遅らせることのないように育てることが成功者の思考なのです。
過去を切り捨て未来を見据えてチャレンジし続ける企業にこそ新しい世界が開けるのです、 まさに「未来思考で今を考える」ことです、「撤退するときは潔く最も順調な時に」、これを常に頭に入れておくこと、これは私の一つの成功法則でもあります。
二極分化の時代到来と言われて久しいですが現に1000万円以上の高所得者層の伸びと300万円以下の低所得者層の伸びが著しく両極端に広がっています、同じ場所に在って同じような内容の飲食店も同様に繁盛店と閑古鳥が鳴く店とに極端に分かれてきています。
同類商品も同業企業も全てが二極分化の大きな流れに飲み込まれているかのように思える現象があちらこちらに見受けられます、そんな時代の経営者もまた時代の流れに逆らえず大きく二極分化してきます、私がここでいう経営者の二極分化とは「勝ち組/負け組」という当りまえな事ではありません、これは企業そのものの評価という意味でのこととなります。
では経営者の二極分化の流れとは何でしょうか、それはその経営者が置かれた空間そのものを意味する「コミュニティ派/孤立派」に大きく分かれていくことにあります。
コミュニティ派の経営者は社員やパートナーに加えて常に各種のコミュニケーションを図れる仲間が多数存在し孤独感を味わうことなく自身の道をひたすら走ることができます、困ったら相談できる、悩んだら話しを聞いてくれる、食事も常に一人ではないから心身共に元気そのものです。
対して孤立派の経営者は友達や付き合う人が多く居るように見えてもいざという時には孤独感に包まれることを意味します、心から気を許す存在が周囲にいないからに他なりません、基本的に人間関係構築が上手くできない結果とも言えるのですが、この現象がここ数年で大きく広がっていきます。
この原因を私なりには分析しており一つは「SNSの功罪」と結びつけて考えています、リアルでも人間関係構築には面倒なことを避けては通れません、だから手軽にコミュニケーションが図れ何時でも面倒になれば縁を切れるバーチャルの世界にのめり込んでしまうのです。
しかしバーチャルはあくまでもバーチャルでしかありません、SNSの世界ではカリスマ的な存在であってもリアルな世界では常に孤独感に襲われます、こんな経営者は珍しくなくなってきたように思えます、孤独感に押しつぶされそこから逃れようと更にSNSの世界にのめり込んでしまいます、結局のところ経営者の「存在二極分化」はこうしてどんどん広がっていくのです。