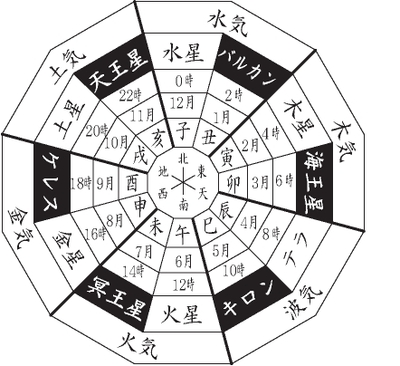2023年9月29日 07:00
水の話し-6
「水」は化学的に見て極めて異質な存在であり、生命に重要な関わりを持っていることを説明してきました。
今回は、いよいよ「生命誕生」の謎に迫りたいと思います。
ここで、興味深い実験を紹介します。
1953年、まだ工科大学院生だったスタンリー・ミラーは彼の師であるハロルド・ユーリーが提唱した「原始地球生成論」を基に35億年前の原子大気の成分とされていたメタン・アンモニア・水素に加えて水蒸気(「水」)の混合ガスに火花放電を行いました。
この火花放電とは彼の仮説の一つでこれらの大気に何かしらのトリガー(引き金=きっかけ)があって、生命に必要な成分(アミノ酸)が生成されるというものに基づいています。
その結果、DNAを構成する物質であるグリシンやアラニンなどの複数のアミノ酸や尿素などが生成されました。
つまり実験によって、初めて原子地球上で自ら生命が誕生したと言う「化学進化論」を実証したのです。
その後、多くの科学者によって、火花放電だけではなく、紫外線・電磁波(放射線)・超音波(波の揺れ)などの刺激によっても同様にアミノ酸などを生成できることが実証されました。
ところが、この後の天文分野の急速なる研究進展によってこの実験が一旦は白紙化してしまうのです。
それは原子地球の大気とされていたメタン・アンモニア・水素などのいわゆる「還元型大気」は当時の太陽活動から計算の結果、強い太陽風で吹き飛ばされて失われてしまっていたということになったのです。
そして地球には火山活動からの「非還元型大気」である現在の地球の大気と同じ二酸化炭素・窒素・「水」(水素+酸素)が充満していたということが判ったのです。
また、これらの「非還元型大気」で実験を繰り返したのですがアミノ酸などが生成しにくいことが解ったのです。
この結果、「地球生命は地球外からもたらされた」とする地球生命の「地球外飛来説」が有力な仮説として今日まで多くの科学者によって支持されてきているのです。
さて、果たして真実はどうなのでしょうか。
地質調査で35億~37億年前には地球上には少なくてもバクテリアや真菌類が生息していたことが解っています。
この生命が誕生したであろう35億年前の地球の大気が「還元型大気」であれば、地球での生命誕生説である「化学進化説」が有力となり、「非還元型大気」であれば「地球外飛来説」が有力となります。
残念ながら、今現在では後者の「地球外飛来説」が有力な説とされています。
では、後者の「地球外飛来説」を支持したとして、一体何処で生命は生まれどのようにして地球に飛来してきたのでしょうか?
また、この地球上に何故これほどまでに「水」が大量に存在するのでしょうか、これは長年の多くの科学者の間では謎として存在し多角的なカテゴリーにより研究されてきました、どう考えても地球には「水」が多すぎるのです。
そしてそれらは最近になって非常に有力な説が幾つも急浮上しています、またこれらの説は極最近になって多くの各種宇宙探査機のデータによって判ってきたことなのです。
つまりこれらの分野はこの数年間で一気に大ブレークしています、数年前の科学雑誌や書籍を読んでも出ていません、それほどまでに急速に変化していることを知っていただきたく思います。
<続く>