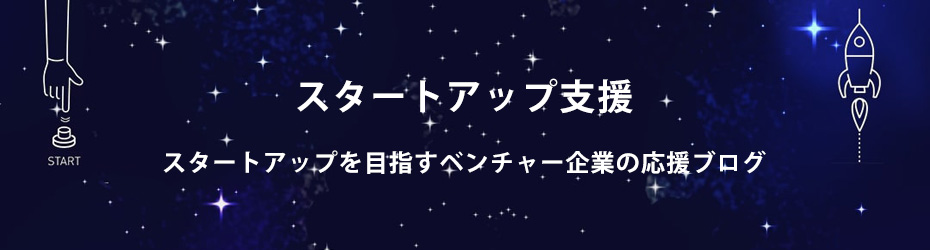売れる作家などは一時期に次々と作品を出してはそのほとんどがヒット作となるのですがピタッと作品が出なくなるときがあります、これがその人の才能の臨界点ということになります、つまり自身の中に培ってきたイメージも含めて蓄えてきたデータを出し切った結果であり私は「才能の枯化現象」と呼んでいます。
ブロガーも同じことがいえます、一時期爆発的に発信していたかと思ったらピタッと発信しなくなる人がいます、おそらく貯め込んできた発想やノウハウを全て出しきってしまったのかもしれません。
ここで思うのですが、どんな業界においても大きなヒットは出さなくも継続してコンスタントにコンテンツを出し続けている人もいます、このような人は臨界点を知らない人であり常に進化と成長し続けている人と言えます。
どちらが凄いとかいう問題ではなく個性の問題だと思います、「太く短く」か「細く長くか」、何れにしても人間の能力にはリミットというものが存在します。
時々どんな業界においてもモンスターと呼ばれる人が存在しています、この人は「太く長く」を継続できる人です、どのようにしたらそれが可能になるのか本人でさえ解らないのかもしれません、私が考えるにきっとその人は人生に対する使命感が強いのではないでしょうか、そんな感じがしてなりません。
起業して売上を上げるためには商品やサービスが売れることが必要です、ところが「売上」とは自分ではコントロールできないものの一つでもあります、当然のこと お客様がいて商品やサービスを買っていただいて初めて「売上」になるからです。
ではどのようにすれば「売れる」のでしょうか、答えは簡単でその商品に「ニーズ」が有れば売れて無ければ売れないということです、ここで重要なポイントは「市場(マーケット)」と「シェア」という考え方です、「市場(マーケット)」はその商品の関連する業種全体の経済規模で、 「シェア」とは市場に占める自社のその商品やサービスの経済規模の割合です。
その商品やサービスが位置している「市場」の規模はどれぐらいで自社は何%の「シェア」を持っているのでしょうか、この2つの問いにズバリ答えられなければ 自身の商品やサービスの売り上げ予測を立てることができずに計画など絵に描いた餅となります、正確な状況を分析し売上予測を立てることで始めて今後の経済活動を計画していけるのです。
自分の会社が市場のどの辺に位置しているのか正確に把握できていますか、まずは客観的に見て自分がどこにいるかを把握することが肝要です、正確な情報を手に入れて分析し計画する、これでようやく最終的に自分はどこへ行きたいのかを見定めることが可能になります、そして結果的に経営方針が決まってくるのです。
闇雲にただ多くの人と会いその場限りの利益活動に翻弄する、これでは経営とは言えません、経営とは99%はテクニックで決まるのです、各種のテクニックを学ばずして場当たり的な行動を繰り返していては自身の目的さえ見失ってしまうのは当然です。
セミナーやワークショップへの動員はできてもメインメニューへの契約になかなか結びつかないというケースをよく見かけます、ところで何故見込み客止まりになってしまうのでしょうか?
この要因を正確に分析できなければこの先何をやっても同じことが繰り返されます、ここで重要な事を忘れてはいけません、それは何の目的のセミナーでありワークショップなのかということです。
セミナーやワークショップだけで利益が上がるビジネススキームなら問題ありません、しかし見込み客獲得の目的であった場合には「成約率」が重要になります。
例えばセミナーに来てくれた人が100人いて本来のメニューの成約者がゼロなら成約率はゼロです、逆にセミナーに来てくれた人がたったの3人でも本来のメニューへの成約者が全員なら成約率は100%になります。
100人のセミナー収益に比べて多くの場合にたった1人のメインメニューの収益の方がはるかに高いと思います、つまり後者の方が売り上げだけでなくコストも軽減されて利益率が高くなります。
セミナーやワークショップが見込み客獲得が目的だとしたら重要なのは参加した人の数ではありません、それは本来のメインメニューを成約してくれる人かどうかという質の問題です、つまり「集める人を間違ってませんか?」ということなのです。
また集客の数を誇るような見栄張りな人は本来のビジネスを見失うことになります、当然ターゲットを絞るのですから募集そのものも限定した人に対してのみ行われなくてはなりません、したがって来る人も少人数になって当たり前なのです、見込み客は数の勝負ではありません、絞り込んだうえでの質で勝負すべきなのです。
「愛は盲目」なんていう言葉がありますがビジネスもこれに近いものがあります、つまり自身のビジネスに集中するがあまり盲目になってしまいビジネスによって自身の思考に大きな偏りが生じてしまうのです。
例えば私は仕事柄クライアント企業の経営的欠点を隠れたデータや決算書から瞬時に探すことができます、経営改善は先ずは隠れた事実と欠点の洗い出し、それから良いところを延ばしていくという順序が最も効率よく改善できるのです。
その思考がクライアントではない企業や人に対しても顔を覗かせてしまってストレスを感じるときがあるのです、考えなくても良いことなのに気になって仕方がなく何か改善する方法はないかと考えてしまうのです。
これは余計なお世話でその企業や人にとっては今のそれが居心地が良いと思っているのだからこのままでいいのです、自身のビジネスによって確実に思考の偏りが生じています、それに気づいて修正しないと思わぬトラブルになることもあります。
それぞれがそれぞれの人生というドラマの主人公なのです、どんな気になることもその人が良いと思ってやっている事であれば他者がとやかく言うことではないのです。
思いたくはないのですがいろいろ人がいます、起業して経営者になったとしても事業の成功を夢見る人だけではないということなのかもしれません。
これから起業する人や新規事業を考えている人に向けて強いビジネスを構築するヒントを幾つか紹介します、少なくても過去から現在までの各種トレンドの流れを掴んで自然に乗ることが最も重要です、ニーズや市場が無ければどんな良いアイデアであってもビジネスはできません、では強いビジネス構築法を幾つか紹介します。
1.「衣食住」は人が生きていく上で必須事項。
人間が存在する以上、確実な市場が存在するのが「衣食住」です。
2.人口比率の高い世代ほど競争意識が高い。
現在の年齢別人口比でいうと1950年生まれと1975年生まれの前後に大きなピークがあります、この世代は子供の頃から自然と競争が染み込んでいると言っても過言ではなく、ビジネスに活かせるヒントも多いです。
3.オリジナルを持つと他者依存が生まれない。
他者と同じことをしないことと、自分だけしかできないことをビジネスにすると他者を意識せずにビジネスでき強いと言えます。
4.各種の権利を得ること。
特許などの知財権は勿論のこと販売権・使用権・複製権などの権利を持ち有効活用するビジネスは強く上手くいけば労せずして半永久に利益を得られます、一度手にした権利は手放すことなく有効活用することを考えましょう、またテクニック次第で資産化することもできます。