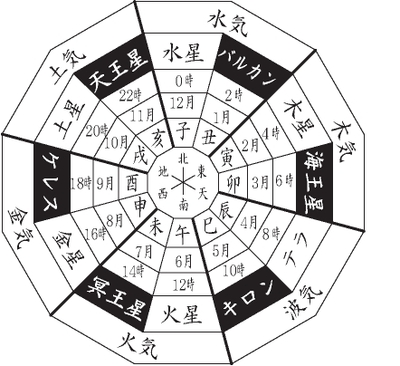2026年2月 5日 07:00
「金気」
「波」の要素と「五行思想」から得られるキーワード = 秋・西・清涼・結実
「元素」の性質から得られるキーワード = 個体・柔軟・形成・疲労
自分で努力しなくても他者から援助や支援されるというような「相続」を受けるという、ある意味での羨ましい気質が「金気」の人の最大の特徴です。
ただし、それは自己利益を排除し謙虚に組織や人の「和を乱さない」ことが条件となります。
ただでさえ何もしなくても目立つ「金気」なので、自分から積極的に獲物を取りにいくような行動をすると「強欲」や「生意気」と写るので周囲から敬遠されることになるので大いに注意を要します。
決して、ねだったり欲しがったりしない方が「金気」らしさの余裕ある穏やかな人に見られるでしょう。
また、「失う怖さ」は「水気」程ではないのですが、一度手にしたものを何かをきっかけに強烈に意識するようなところがあり、「失う」・「減る」ことに異常な恐怖を感じる人もいるでしょう。
ただ、そんなときでも「金気」は決して表情や言葉に出してはいけません、余裕を持って極自然に振る舞うことが「金気」らしさを維持することができるのです。
他の人に真似できないような、「個性」豊かなファッションでも嫌らしくならないのもこの「金気」の性質の一つです。
ただこれも自然に自分流でやっているうちは良いのですが、余りにも意識して自分で作り上げていくような無理が出ると一転して嫌らしさが出ることがあります。
「金気」は謙虚に極自然に振舞っていればよく、自己主張や無理して欲しい物(者)を得ようとしないことが肝要です。
つまり「金気」の成功のキーワードは、「収穫を得られるまで、自ら動かずじっと待つ」姿勢です。
「金気」の人は自分磨きにも積極的です、いろいろな事に興味を引かれ、またそれを器用に実践していくでしょう。
ファッションや資格といった、自分を見た目で評価されるものに大変興味を持つのですが、そういう表面的なことではなく心の豊かさや優しさ、そういうものを鍛えると本当に輝ける「金気」の人になります。
そもそも、人を惹きつけ好かれる素質を持ち合わせていますので、人間としての正道に徹して、義理や人情、恩や礼というものを大切にして豊かで正常な人間関係を構築することが肝要です。
最後に、「金気」の最大なる注意点はストレスです。
本来「金気」の人は、精神的にも肉体的にも割りとストレスに強いのです、また身体が柔軟な人も多いのであまり疲れを意識しない人も多いでしょう。
しかし、ストレスは確実に「金気」の人の心身に蓄積されていきます、意識しないが為に、他の気質のようにマメなストレス発散もしません、しかし一旦ストレスが表面に出たときは一気に心身を壊すことになります。
「ストレスを溜めないこと」、これが「金気」らしく何時までも輝いていける方法です。
そのストレスの最大の原因、それは自分自身が作り上げている心の中の理想と現実のギャップに起因しているのです。
あくまでも自ら動きまわるのではなく、「収穫をじっと待つ姿勢」を忘れずに、肩の力を抜いて周囲に元気さを振りまくだけで全てが好転します、そして自身も楽に生きられるのです。
自らは決して獲物や収穫を追わないこと、「金気」の人が成功するのは自ら何かを成し得るような行動からではなく謙虚に務め最終的に他者から「相続を受ける」ことにあるのです。
自身が表面に出て活躍するとすれば、相続を受け成功した後に一気に行うことです。