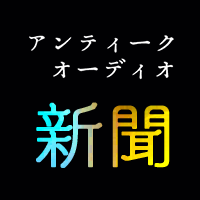ロクハンとは、6.5インチ口径のスピーカーユニットを指しています。
6.5インチ=16.5Cmで、いつしか16Cm口径のスピーカーユニットをロクハンと呼ぶようになりました。
今現在の自作スピーカーでは小型で扱いやすい8Cmや10Cmが主流のようですが、70年代では16Cmや20Cmが主流でした。
当時は、フォステクス、コーラル、テクニクスがスピーカーユニットの3大ブランドで、歴史に残るような名ユニットが多数生まれました。
現在では、コーラルがバブル景気終焉後に倒産し、テクニクスはユニット事業から撤退、結局日本の本格的オーディオスピーカーメーカーはフォステクスしか残っていません。
フォステクスは、今や世界的な一流ブランドとして君臨しています。
※本シリーズは、オーディオ用語辞典には載っていない往年のオーディオマニアの間で使われている用語を紹介しています。
近年でもオーディオ誌の評価レポートなどにおいて、往年のオーディオ評論家が使うこともありますので参考になれば幸いです。

ゴリゴリとは、極めて硬質系の低音を放つアンプやスピーカーの音質を言い表したものです。
例えばサンスイの80年代のアンプの音質は、低域が独特の硬質で更にレスポンシビリティが極めて高く、ベースを聴くと「ブン、ブン」ではなく「ッブンッ、ッブンッ」と切れが良くメリハリのある音がします。
これを言葉でどう表現するかというと極めて難しく、そこで生まれたのが「ゴリゴリ」という擬音だったわけです。
確かに、これはよく言い表した表現だと思います。
指力が半端ではないロン・カーターのピッコロベースをサンスイのアンプを通して聴くと、本当に「ゴリンゴリン」と弦の弾く音が聞えますから。
※本シリーズは、オーディオ用語辞典には載っていない往年のオーディオマニアの間で使われている用語を紹介しています。
近年でもオーディオ誌の評価レポートなどにおいて、往年のオーディオ評論家が使うこともありますので参考になれば幸いです。

ヒゲとは、鋭いパルス状のノイズや音のことで、波形をシンクロスコープなどで観測すると髭のように見えることから命名された。
レコードをかけているときの、「パチッ」とか「プッ」という感じのノイズをスクラッチノイズと呼びますが、多くは静電気やレコード表面の傷などが原因です。
また、アンプやスピーカーでの接触不良を起こしている場合も、単発的な鋭いノイズが入る事もあります。
こういった場合に「今、ヒゲ乗ってなかった?」などと言います。
※本シリーズは、オーディオ用語辞典には載っていない往年のオーディオマニアの間で使われている用語を紹介しています。
近年でもオーディオ誌の評価レポートなどにおいて、往年のオーディオ評論家が使うこともありますので参考になれば幸いです。

打ち込み系とは、シンセサイザーやドラムマシンなどに予め音符を打ち込んでおき、それを再生する事で演奏する電子音主体の曲のことを言います。
反意語的に用いられるのがアコースティックで、こちらは電気を使わない生の楽器演奏を指します。
例えば、バイオリンやギター、ベースやチェロなどです。
電子楽器の音は独特な特性(波形)を持つので、アンプやスピーカーの音質確認には必ずリファレンスソースとして組み入れられるのが普通です。
近年の多くのポップスやユーロビートにフュージョン(進化系ジャズ)などが、音楽的なジャンルとしては打ち込み系と言えるものになります。
※本シリーズは、オーディオ用語辞典には載っていない往年のオーディオマニアの間で使われている用語を紹介しています。
近年でもオーディオ誌の評価レポートなどにおいて、往年のオーディオ評論家が使うこともありますので参考になれば幸いです。

箱鳴りとは、スピーカーにおいてユニットの振動でエンクトージャー自体が振動し音を発する状態を言います。
PA用のサブウーハーは、敢えて箱鳴りするようにしてステージ全体を振動させ重低域を響かせる設計の製品があります。
しかし、ハイファイオーディオの世界では箱鳴りはNGです。
ユニット自体の音に加えてエンクロージャーの振動による音が合成され、変なところが持ち上がったり歪を生んでうるさく聞こえるような音質になるからです。
また、置き方によっても大きく音質が変化してしまいます。
エントリークラスのスピーカーは確実に箱鳴りします、これは音を鳴らしているときにエンクロージャーの横を手で触ってみれば解ります、手に振動を感じたら箱鳴りしています。
ハイエンドのスピーカーは、大きな音で再生しても振動するようなことは一切ありません。
※本シリーズは、オーディオ用語辞典には載っていない往年のオーディオマニアの間で使われている用語を紹介しています。
近年でもオーディオ誌の評価レポートなどにおいて、往年のオーディオ評論家が使うこともありますので参考になれば幸いです。