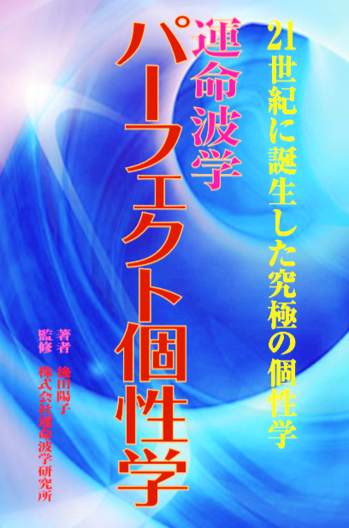2025年7月21日 08:00
金の話し-3
その他の「金属」の持つ大きな特徴としては「熱伝導性」があげられます、これは読んで字のごとく熱を伝達する特性です。
この「熱電動性」という特性は、工業用途だけではなく、我々の生活の中にもたくさん利用されています。
ボイラーや湯沸かし機ではその特徴を存分に発揮しています。
他の物質ではエネルギーの損失が大きく、同じ温度にするのに「金属」の何倍もの燃料を要します。
「金属」の「熱伝導」を可能にする性質は「伝導電子=自由電子」が存在するためで、メカニズムは原子の激しい振動によって起こります。
「金属」の一部を熱すると、原子が熱を帯び「伝導電子」が激しく震動します、この震動が次々に隣り合った原子に引き継がれていきます、これによって熱が素早く伝達されるのです。
対して、岩石や焼き物(土)の場合はその構成原子そのものが温められ熱の伝導が行われます。
この場合は、ゆっくりと熱が伝わりますが、逆に冷めにくいということも言えます。
「金属」は「伝導電子」によって素早く熱を伝えますが、逆に冷やす時も同じであっという間に冷えていきます。
早くお湯を沸かすなら「金属」、ゆっくりでも冷めないようにするには石や焼き物(土)を使えばよいのです。
石鍋や土鍋は逆にこの冷めにくい性質を利用しているのです。
この「熱伝導性」の性質は「金」の気質そのものにも生きてきます、つまり「熱しやすく冷めやすい」という陰陽の極みが表面化してしまいます。
これを逆手に「金」の気質の人は粘り強く待つ姿勢が求められ、これを獲得できた「金」の気質の人は美的センスに加えて、鋭い感性と強靭な強さを誇り、まさに無敵、怖いものなしの金字塔を構築できるでしょう。
「金」の人がこれをいとも簡単に実現できる方法が有るのです、それは次回にじっくりとお話ししましょう。
<続く>