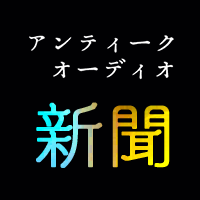ELEKIT(エレキット)は、株式会社イーケージャパンのオーディオブランドである。
1973年、嘉穂無線株式会社から分社して電子工作キットを手掛けるメーカーとして誕生する。
その後、教材用のラジオキットなどで有名になり、オーディオアンプのキットなども出すようになる。
現在も、真空管アンプキットなどでオーディオ製品を出しており、2014年に嘉穂無線株式会社に再び吸収されたが、ブランドとしては現在も存在している。
真空管アンプでは、本格的なスペックで音質も確かなものでありファンを増やしている。
尚、完成版も同時に発売される製品もあり、メインシステムで使うマニアもいる。

Nakamichi(ナカミチ)は、かつて存在していたナカミチ株式会社のオーディオブランドである。
1948年に創業し、録音装置では技術力を誇りオープンリールデッキやカセットデッキでは高級製品を出し、世界のオーディオブランドとなった時期もあった。
70年代、80年代にはアカイ、ソニーと共にオーディオ界の録音機器ブランドの三大ブランドとして世界に名を馳せた。
オープンリールデッキでは、いまだにメンテナンスを施し愛用しているマニアも多く、オープンリールデッキやカセットテープデッキの高級ハイエンド部門では名機を数多く誕生させた。
また、ハイエンドセパレートアンプを出していた時期もあり、このハイエンドアンプは日本ではあまり知られてないが世界中のマニアを魅了した。
2008年のアメリカのオーディオ誌の人気アンケート調査で、B&O、Boseに次ぐ3位を獲得したほど世界では超有名なオーディオブランドを確立したしていた時期もあった。

ALPINE/LUXMAN(アルパインラックスマン)は、カーオーディオ大手のアルパイン株式会社のホームオーディオブランドである。
1981年、アルパイン株式会社がラックスマン株式会社を資本傘下に収めた後、1985年から6年ほどホームオーディオ製品をALPINE/LUXMAN(アルパインラックスマン)ブランドで市場に出したことがある。
製品としては、真空管とトランジスタのハイブリッドプリメインアンプを引っ提げてアンプ798戦争に参戦し、当時のラックスマンファンを驚かせた。
たったの数年間のホームオーディオブランドで、これといった大きな実績としては他に残していない。

AIWA(アイワ)は、現在十和田オーディオのブランドとして引き継がれているオーディオブランドである。
元々は、アイワ株式会社のブランドで、1969年にソニーのグループ企業となり、ラジカセを中心としたオーディオ製品で大きなシェアを誇っていた。
AIWA(アイワ)ブランドは、2008年に一旦終焉するが、2015年にアメリカで復活する。
2017年、同ブランドの商権を獲得した十和田オーディオが同ブランドでオーディオ製品を出しているが旧ブランドとの関係性は無い。

CORAL(コーラル)は、かつて存在していたコーラル音響株式会社のオーディオブランドである。
70年代、80年台を通しフォステクス、テクニクスと共にDIYスピーカーユニットを供給した3大スピーカーユニットメーカーの一つ。
初期の頃はアンプや一体型ステレオなども手掛けていたが、徐々にスピーカーユニットやスピーカーシステムに注力するようになる。
音に対する技術力を高く評価されたが、経営戦略が後手に回り倒産の道を辿ることになる。
いまだにスピーカーシステム等が中古市場に出るとあっという間に売れてしまうほど、絶大なコーラルファンが存在する。